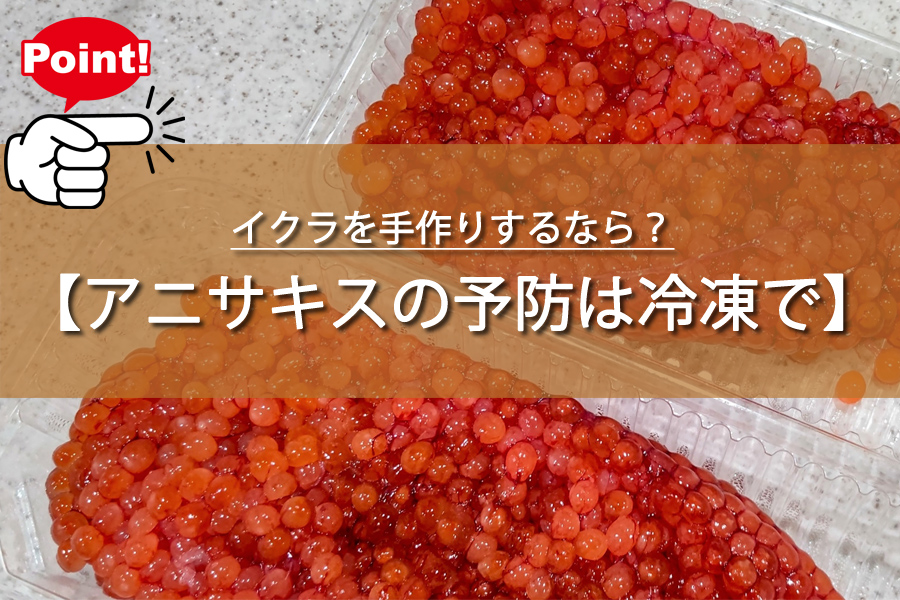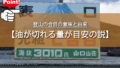イクラと言えば、手作りする人も多いけど…
アニサキスの心配はないのかな?

アニサキスは冷凍すればOKと聞くし、管理が良ければ大丈夫よ。
今回は、イクラのアニサキスを予防する方法など紹介するわ!
いくらに限らず、魚の場合、寄生虫のアニサキスがいると食中毒の原因にもなりますが、予防法を知っておけば、対処もできますよね。
今回は、イクラのアニサキスを予防する方法などご紹介します!
イクラのアニサキスは冷凍すればOK?

イクラは市販されているものにアニサキスが入ってることはめったにありません。
ただ、もし少しでも可能性を減らしたいなら、アニサキスは冷凍(-20度で24時間以上)放置すると死滅します。
ちなみに、ご家庭の冷凍庫では、-15度までが限界のケースも多く、この場合は完全に死滅するとは限りません。
手作りのイクラは大変美味しいですが、アニサキスが気になるなら、先に筋子を冷凍して24時間以上置いたものを使うにしてください。
加熱でもアニサキスは死滅する
イクラの場合、加熱して食べるのは難しいかもしれないですが、アニサキスは加熱でも死滅します。
もし加熱するとしたら、お湯を使ってイクラを作れば大丈夫なことも多いんですね。
ちなみに、アニサキスを死滅させたいなら、60℃で1分以上の加熱が目安です。
アニサキスは醤油や塩では死滅しない
アニサキスは寄生虫なので、濃い塩分濃度で死滅しそうな気もしますよね。
ただ、アニサキスは、醤油や塩、酢でしめても死滅はしません。
また、ワサビなどの香辛料にも死滅させる効果はないので、イクラの醤油漬けや刺身など、生で食べる時には気を付けましょう。
内臓を摘出する方法も
アニサキスは、冷凍や加熱の他にも、新鮮なうちに魚介類の内臓を摘出する方法があります。
なぜ内臓を抜くと安全かと言えば、内臓に寄生するアニサキスの幼虫は、魚介類が死ぬと筋肉へ移行する性質があるからです。
ただ、これでも100%安全とは限らないので、やはり予防策としては、冷凍か加熱が一番安心かなと思います。
イクラを安全に自宅で作る方法

イクラを自宅で作るなら、事前に筋子を冷凍しておくと、アニサキスの心配は減ります。
それを踏まえたうえで、イクラの安全な作り方を見ていきましょう。
手順①すじこの筋・薄皮と卵
まず、網(100円ショップでも手に入る)を丼の上に乗せ、上に生筋子を置いたら、上から円をかくように押さえつけると、卵がバラバラに丼に落ちて作業が簡単になります。
卵が割れそうと思うかもしれないですが、網目がやや粗いタイプなら、問題なく落ちてくれるので、どうしても心配なら、手でほぐす方法もあります。
手順②食塩水で洗う
筋子の卵がバラバラになったら、塩分濃度1~3%の食塩水でさっと洗って、筋子に付着した汚れを取り除きましょう。
筋が取れるようになったら、手で筋を取り除き、ざるに開けると簡単です。
手順③お湯でアニサキスを死滅させる
アニサキスを予防するため、中心部分が60度で1分間加熱、もしくは70分加熱してアニサキスを死滅させましょう。
1分が過ぎたら、温度計でお湯の温度を測り、60度以上あればOKです。
ちなみに、お湯の温度が90度を超えてしまうと、イクラが割れてしまうので、熱すぎない温度にすることが大切です。
手順④冷やして味付け
イクラをざるにあけたら、氷水に入れて冷やしますが、この時イクラが少し白くなります。
白くなったら「失敗した?」と思うかもしれませんが、透明感は味付けすれば復活するので気にしなくても大丈夫です。
イクラの味付けでは、液が「3:1」または「2:1」の割合になるようにするのがポイントです。
具体的には、300gのイクラを作るなら、味付けの液は100~150g必要となります。
後は、水気を切ったイクラを味付け液に漬け込み、冷蔵庫で半日~1日冷やせば、美味しいイクラの完成です。
イクラのアニサキスの予防法は冷凍だけじゃない! まとめ
それでは、イクラのアニサキスを予防する方法や自宅で安全に作る方法などご紹介してみました。
市販の冷凍筋子なら問題ないですが、釣りに行ってすぐに調理するなどの場合、アニサキスが気になりますよね。
もし、アニサキスが気になるなら、一旦冷凍する方法が一番確実なので、イクラを作る時には注意してみてください。
最後までお読みいただきありがとうございました!