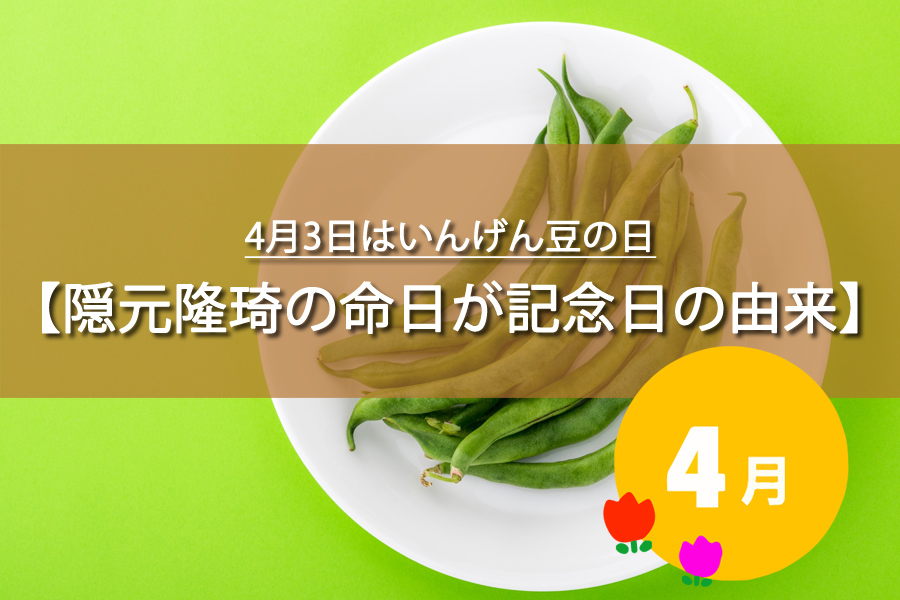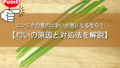4月3日はいんげん豆の日だね!
僕はどうも豆が苦手なんだけど、栄養価も高いらしいね。

中国から伝わった豆で、健康にも良いみたい。
今回は、4月3日がいんげん豆の日になった由来など紹介するわ!
4月3日は、「いんげん豆の日」とされています。
この日に込められた意義や背景について解説します。
いんげん豆の日(4月3日)

この記念日は、1673年4月3日に中国から日本へいんげん豆を持ち込んだとされる隠元隆琦が逝去した日にちなんでいます。
日本においては、徳川家綱の厚遇を受け、京都宇治に萬福寺を設立。
いんげん豆を含む多くの中国文化を日本に伝え、その一つとしていんげん豆の普及に貢献しました。
いんげん豆の種類
いんげん豆は、若いさやを食べるサヤインゲンと豆のみを食べるインゲン豆に分けられ、白いんげん豆や金時豆もこれらの仲間です。
クセが少なくどんな料理にも合わせやすい野菜であり、特に関西地方では三度豆とも呼ばれています。
いんげん豆の選び方
いんげん豆の選び方には、鮮やかな緑色で実が小さく、弾力がありポキンと折れるものを選ぶと良いでしょう。
黄色くなっているものや、さやが堅いものは避けましょう。
いんげん豆の保存方法
保存方法は、損傷したものを取り除き、袋に入れて野菜室に保管します。
下処理して冷凍しておくと、様々な料理に便利に使えます。
いんげん豆のおいしい食べ方
おいしい食べ方としては、塩茹でした後に冷水で冷やしてから、様々な料理にアレンジします。
さやいんげんは副菜や洋食の付け合わせに多用されがちですが、その美味しさと栄養バランスを活かして主菜としても堪能したいものです。
さやいんげんに含まれる栄養素
さやいんげんに含まれる栄養素には、ビタミンAやB群、C、ミネラル、食物繊維、高品質のタンパク質、免疫力を向上させるレクチンなど、健康維持や生活習慣病予防に役立つ成分が豊富に含まれています。
追加情報
サヤインゲンには、つるがある品種とつる無し品種があります。
つる無し種は収穫までの期間が短く、年に複数回収穫できることから「三度マメ」とも呼ばれています。
一般的な丸さやタイプのサヤインゲンの他に、モロッコインゲンのような幅広いタイプも存在します。
「ささげ」と見た目が似ているものの、異なる品種群に属し、アフリカが原産地です。
夏の暑さによる体調管理に「インゲン」
夏の暑さは食欲不振や疲労を引き起こし、体調を崩しやすい時期です。
そんな時期にインゲンは役立つ栄養素を多く含んでいます。
β-カロテンが皮膚や粘膜を保護し、夏の日焼けによるダメージ予防にも有効です。
薬膳の観点からも、インゲンは体内の不要な湿気を除去し、胃腸の調子を整えたり食欲不振や夏バテを防ぐ効果があるとされています。
夏だけでなく、夏の疲れが残る初秋にも、インゲンは体調を整えるのにおすすめの食材です。
「サヤインゲン」と「インゲンマメ」の違い

「インゲン」と一般的に言われる時、それは通常サヤインゲンを指します。
サヤインゲンは、未成熟のインゲンマメであり、さやごと食べることができます。
一方、インゲンマメとは成熟したサヤインゲンの豆のみを指し、料理の方法も異なります。
サヤインゲンは茹でたり炒めたりしてそのまま食べられますが、インゲンマメは煮豆や甘納豆などに加工されることが多いです。
いんげん豆を食べて体調も改善 まとめ
「いんげん豆の日」の意味や由来などご紹介してみました。
いんげん豆は、元々日本にはなかった豆ですが、栄養価が高いことから近年人気が出ています。
ぜひ、記念日にはいんげんを食べて、健康効果などをたっぷりと受け取りましょう。
最後までお読みいただきありがとうございました!