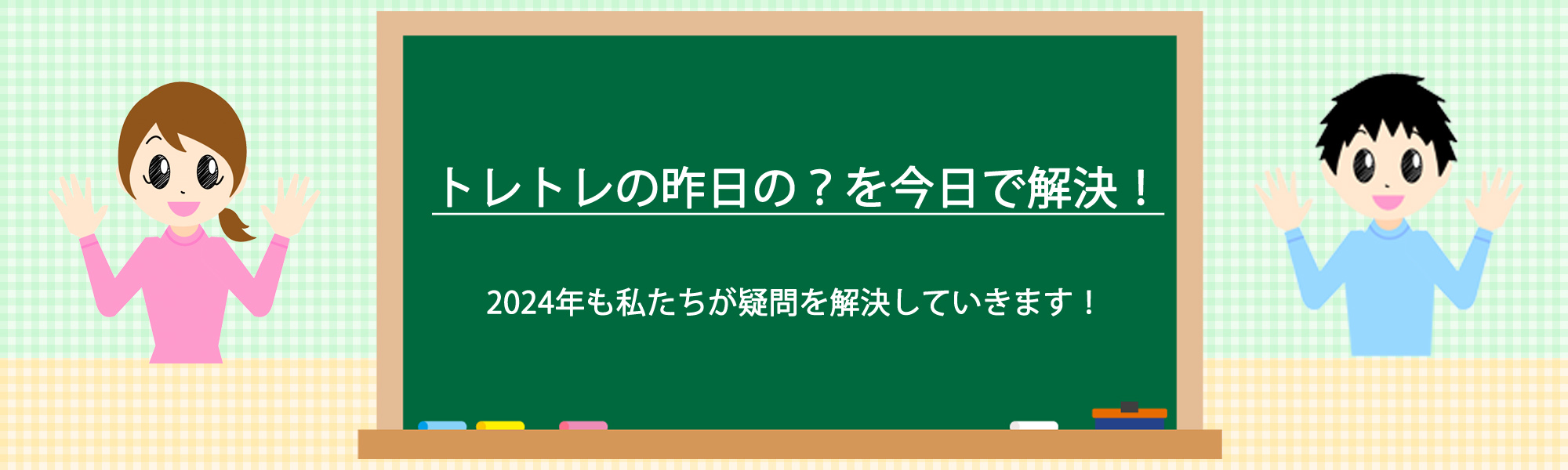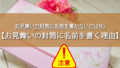正月っぽいメニューと言えば、やっぱりおせちだよね。
でも定番料理にもちゃんと意味があるのが日本らしいよ!

おせち料理の定番メニューは、確かに意味が深いわよね。
今回は、正月っぽいメニューとして、おせちに込められた意味など紹介するわ!
黒豆や数の子、田作りなど、日本の伝統的なお正月料理には様々な願いが込められています。
これらの料理の背景にある歴史と意味を知り、新年を迎える準備を始めましょう。
伝統的なお正月料理とその背景にあるストーリーを紹介します。
正月っぽい?5つのカテゴリー別お正月料理

お正月料理は「祝いの一品」「口取り」「焼き料理」「酢のもの」「煮物」の5つのカテゴリーで構成されています。
それでは、それぞれのカテゴリー別に代表的な料理を紹介します。
祝いの一品は、お正月料理の中で最初に楽しむお酒の肴です。
邪気を払い、お屠蘇と共にいただくことで新年の幸せを願います。
①口取り
口取りは、甘みのあるお酒の肴で、特に子ども向けのお正月料理としても人気です。
彩り豊かな食材が使われるのが特徴で、お餅や餡を使ったお菓子が一緒に楽しまれることもあります。
- かまぼこ
- 栗甘露煮
- 伊達巻き
- 昆布巻き
②焼き料理
焼き料理は、お正月料理の中でも主役となるカテゴリーです。
縁起の良い海の幸を中心に、焼き上げた料理が楽しまれます。
特に魚の姿焼きが人気で、調理法としては塩焼きや西京焼きが好まれます。
- 鯛の姿焼き
- 伊勢海老の姿焼き
- サーモンの塩焼き
③酢のもの
酢のものは、食事の最中に口をさっぱりとさせる役割を果たすお料理です。
野菜や海の幸を使い、彩り豊かに仕上げられています。
- なます
- 酢れんこん
- ちりめん山椒
④煮物
煮物は、根菜やキノコ類などの山の幸を使って作られるお料理で、お重の最後の段に飾られることが多いです。
肉を加えた煮物もあり、飾り切りが施されることで一層華やかな印象を与えます。
- 煮しめ
これらの料理を通して、日本のお正月を彩り豊かに、そして意味深く迎えることができます。
おせち料理の背後にある深い意義

各々のおせち料理には、幸運を招く象徴や、昔からの人々の願いがしっかりと込められています。
日本の伝統には、縁起を重んじる風習が色濃く反映されています。
以下に、おせち料理に隠された意味と願いを簡潔に説明します。
黒豆(お祝いの肴)
黒豆は醤油と砂糖で煮たおせち料理で、黒色は昔から邪気を追い払う色とされています。
これには「日焼けするほど元気に働けますように」という願いが込められており、また「まめに働く」年になりますようにという願いも含まれています。
数の子(お祝いの肴)
数の子はニシンの卵を使ったおせち料理で、豊富な卵の数から子孫繁栄を願う意味があります。
また、「二親」を連想させ、両親の長寿を願うとも言われています。
田作り(お祝いの肴)
田作りはカタクチイワシの稚魚を使った料理で、昔は農地の肥料として利用されていたことから豊作を祈る意味があります。
特に関東地方で好まれるお祝いの一品です。
たたきごぼう(お祝いの肴)
ごぼうを優しい味付けで調理したたたきごぼうは、棒で叩いて開く調理法から、開運を願う意味が込められています。
関西地方では、これを食べて家や家業の繁栄を願います。
紅白かまぼこ(口取り)
紅白かまぼこは白身魚のすり身を蒸して作られ、その半円形は日の出を象徴しています。
赤は魔よけ、白は清らかさを意味しており、伝統的な「右紅左白」の盛り付けが特徴です。
栗きんとん(口取り)
栗きんとんは栗とさつまいもをペーストにした甘いおせち料理で、黄金色に染められ、富と財産の象徴とされています。
また、「勝ち栗」の語呂合わせから、勝負運を祈る意味もあります。
伊達巻(口取り)
伊達巻は卵と魚のすり身を組み合わせて焼き上げた華やかな料理で、見た目が巻物に似ていることから、知識増加や学業成就を願う意味があります。
また、派手好きな伊達政宗に由来するという説もあります。
昆布巻き(口取り)
昆布巻きは春を告げる魚を昆布で巻き、かんぴょうで結んだ料理で、「よろこぶ」や「養老昆布」「子生」などの語呂合わせから、長寿や子孫繁栄を願う意味が込められています。
鯛の姿焼き(焼き物)
鯛の姿焼きは七福神の恵比寿様が持つ魚であり、縁起が良いとされています。
頭から尾まで一続きであることから、物事を最後までやり遂げる意味もあります。
伊勢海老の姿焼き(焼き物)
伊勢海老の姿焼きは、曲がった腰と長いひげから不老長寿を願う料理です。
また、何度も脱皮することから、立身出世を祈る意味もあります。
ブリの照り焼き(焼き物)
成長とともに名前が変わるブリは出世魚として知られており、その照り焼きは立身出世を願う料理として食されています。
鮭の塩焼き(焼き物)
鮭の塩焼きは、語呂合わせで災いを避ける意味が込められています。
また、生まれた川に戻って産卵する習性から、立身出世を願う意味もあります。
紅白なます(酢の物)
紅白なますは細く切った人参と大根を甘酢で味付けした料理で、慶事に使われる紅白の水引を模しており、おめでたい意味を持っています。
酢れんこん(酢の物)
酢れんこんは輪切りにした茹でれんこんを酢で和えた料理で、穴が空いていることから未来を見通せるように、また、一年中穴が開いていることから無病息災を願う意味があります。
他にも、黒豆や数の子といった食材は、日本の伝統と歴史を色濃く反映しています。
おせち料理を通して、祝福と共に未来への願いを込めることができるのです。
正月っぽいメニューで祝うなら? まとめ
お正月の幸せを願って作られる、意味深い日本の伝統料理、おせち。
この記事で紹介されている様々な料理の背景を知り、自分でおせちを作る楽しさに挑戦してみましょう。
歴史ある風習や先人たちの思いを学びながら、毎年のお正月が待ち遠しくなることでしょう。
最後までお読みいただきありがとうございました!