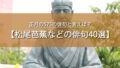鏡開きは、年度や地域によって違いがあるみたいだね。
例えば、2024年の場合、鏡開きはいつになるのかな?

日時などは関西と関東で大きく分かれるみたいなのよね。
今回は、2024年の鏡開きはいつになるのかなど紹介するわ!
「鏡餅開き」という風習は、一体いつから行われているのでしょうか?
今回は、2024年の「鏡餅の取り扱い」が具体的にいつ実施されるのか、さらにこの伝統の背景や意義について触れてみたいと思います!
2024年の鏡開きはいつ実施される?

通常、鏡開きは1月7日の「松の内」が終わってから行われますが、地域差が存在しています。
関東地方では松の内が1月7日まで、一方で関西地方では1月15日までとされていますので、それぞれ鏡開きの日も異なります。
鏡開きは一般的に松の内が終わった後に行われるので、以下のように取り扱われるんですね。
- 関東(北海道も含める):1月20日(松の内は1月15日まで)
- 関西:1月11日(松の内は1月7日まで)
このように、関東と関西では日付が異なるのです。
ただ、特例として京都では、1月4日(木)に鏡開きが実施されます。
なぜ1月4日になるのか調査してみましたが、はっきりとした理由は見つけられませんでした。
京都では、正月3日目が終わるとすぐに鏡開きの儀式が行われるという風習が今も続いています。
ちなみに、日本最北端の北海道では、関東地方と同日に実施されます。
地域によって日にちが異なる理由とは?
関東と関西で鏡開きの日が異なる背後には、武士の社会と商人の社会の差が影響しています。
鏡開きはもともと全国で松の内が終わった旧暦1月20日に行われていました。
その後、松の内を1月7日までとし、鏡開きを1月11日に設定されます。
しかしこの変更は、遠くの関西地方まで広がることはありませんでした。
これが地域ごとの鏡開きの日の違いの原因です。
鏡開きの餅をどのように楽しむ?

鏡餅と一言で言っても、現代では大小様々なサイズがありますが、この鏡餅には、正しい割り方があるんです。
実際、鏡餅を割るときには特定のルールが存在します。
絶対に刃物を使ってはいけません!
刃物を使用しない理由は、武士道精神が影響しており、腹を切るイメージが含まれているからです。
また、鏡餅には年神様が宿っていると信じられています。
なので、神様に対して刃物を向けることは失礼とされています。
正しい鏡開きの方法
正しい鏡開きの方法は「手や木槌を使って割ること」です!
もし餅が固いようであれば、電子レンジで温めるか、水に漬けて柔らかくしてから割るのも一つの手です。
食べ方は、鏡開きの日にお雑煮、ぜんざい、おしるこ、お餅ピザなどにして、年神様の力を取り込みながら味わいます。
「鏡餅の取り扱い」とは?
「鏡餅の取り扱い」は、新年の期間に神様や仏様へと奉げられた鏡餅を取り外して享用する行事とされ、日本の新年の習慣として定着しています。
年神様が宿ったとされる鏡餅を、おしるこやお雑煮などにして、神仏への謝意を表しながら食べることで、年神様からの恩恵を家族全員で分け合うことができると信じられています。
江戸時代にこの風習が広まりました。
商業家では、物置を開ける行事の一環としておこなわれ、武士の家では武具や防具に対して、また女性たちは鏡台に対して行っていたようです。
鏡餅はその後、お雑煮などの料理に使用されていました。
なお、「鏡餅の取り扱い」は、もともと武士道の慣習が庶民に普及したものです。
例を挙げると、江戸城では鏡餅はおしることして料理されていました。
鏡開きの日時が関西と関東で違う理由 まとめ
それでは、鏡開きの日時が関西と関東で違う理由などご紹介してみました。
「鏡」は円満を表し、「開く」は広がりを表します。
また、「切る」「割る」は縁起が悪いため、「開く」という言葉が使われています。
地域によって鏡開きの日が異なる背景には、徳川家光の死が関わっていましたね。
もし結婚や仕事で引っ越しをすることがあるならば、鏡開きのスケジュールについて、事前に地元の人たちに確認しておきましょう。
最後までお読みいただきありがとうございました!