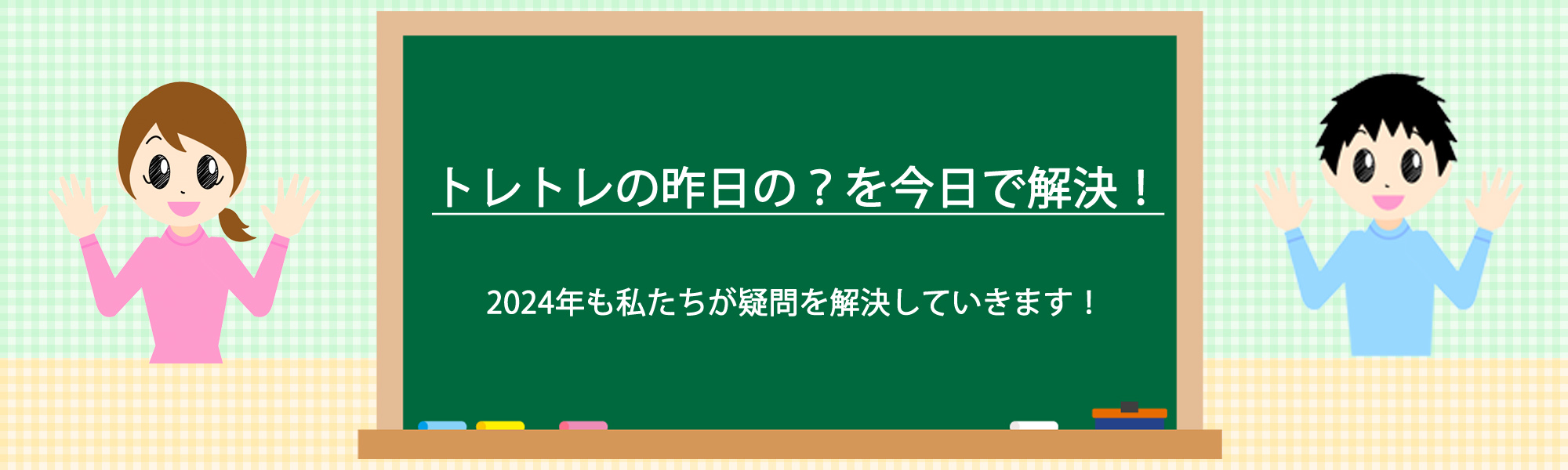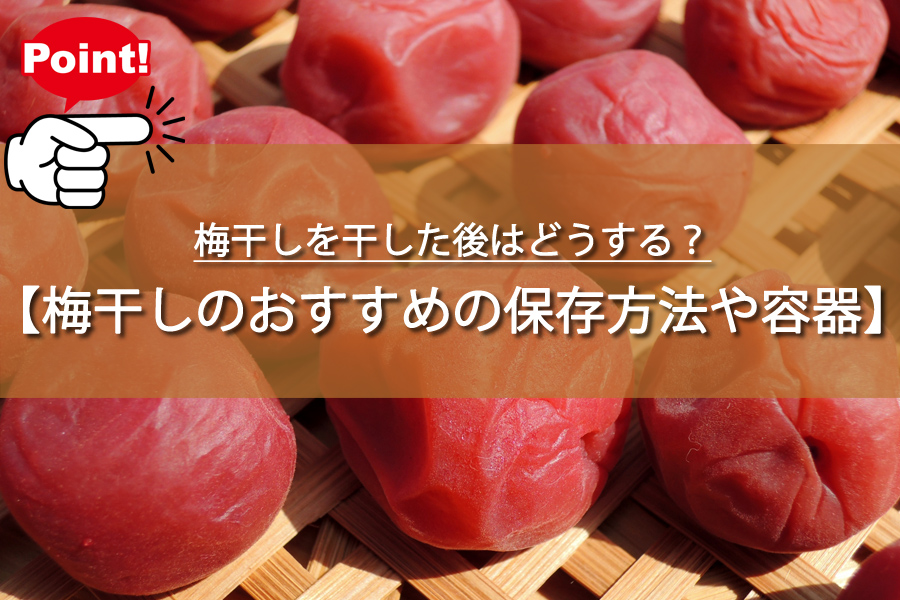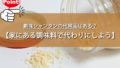自家製の梅干しは美味しいけど、作って干した後はどうすればいいのかな?
できれば、カビが生えないように保存したいんだけど…。

確かに、せっかく作った梅干しだから、ちゃんと保存したいわよね。
今回は、梅干しを干した後の処理方法など紹介するわ!
梅を塩で漬け込み、シソを加えて干した梅干し作りもいよいよクライマックスですね。
ただ、干した後の処理に困っている方もいるかもしれませんね?
今回は、干した後の梅干しの取り扱い方について詳しく説明していきます。
干した後の梅干しはどうやって管理する?

最初に、梅干しがきちんとできているかどうかの判断方法をご紹介します。
一般的に梅干しを干す期間は3日程度とされていますが、時には予想より水分が残っていたり、逆に乾燥しすぎていることもあります。
そんな時、本当にうまくいったのか不安になることでしょう。
果皮がやわらかく、皮の表面にしわがつまむことができれば、それは成功のサインです。
できあがった梅干しの処理
できあがった梅干しは、湿気の少ない涼しい場所にある保存容器に入れて保管します。
新しくできたばかりのものでも食べることができますが、少し青臭さが残っていることがあります。
それを避けるためには、半年以上寝かせておくと良いでしょう。
さらに3年経過すると、味が丸くなります。
干した梅干しはそのままで保存が可能
梅干しを干し終えたら、そのままの状態で空の保存容器に入れておくだけでOKです。
表面は乾燥しているように見えても、内部には水分が残っています。
このまま保管しておくと、梅干しは自然と適度な湿り気を帯びてきます。
もし「梅干しは柔らかい方が好き!」という人は、梅酢を使って調整することもできますよ。
梅干しを長持ちさせる保存のコツ

以下に、梅干しを上手に保存する方法に焦点を当て、その詳しいプロセスを説明していきます。
梅酢の量を変えることで、梅干しの食感や味わいが変わってくるので、自分の好みに合わせて方法を選んでみてください。
保存方法①:乾燥気味でねっとりした食感を楽しむ
この方法は、乾燥した感じの梅干しを好む方にピッタリです。
【やり方】
- 梅干しを乾燥させた後、何も入れていない保存容器に移す
- 梅干しの間に赤シソを入れる
- 容器の蓋をきちんと閉じて密封する
通常、梅干しは3日間ほど日光にさらして乾燥させますが、時には予想以上に乾燥してしまうことがあります。
ですが、乾燥した状態で保存容器に入れておくと、徐々に湿度を取り戻して食感が改善されますので心配は無用です。
ただし、きちんと密封できる容器を使用しないと、梅干しの水分が逃げてしまう可能性があるので注意が必要です。
また、赤シソは乾燥させても問題ありません。
保存方法②:柔らかな梅干しを楽しむ
この方法は、柔らかい食感の梅干しを楽しみたい方におすすめです。
【やり方】
- ボウルに梅酢を入れる
- 梅干しをボウルに入れ、数秒間浸す
- 梅干しをボウルから取り出し、何も入れていない保存容器に移す
- 梅干しの間に赤シソを入れる
- 容器の蓋をきちんと閉じて密封する
梅干しが乾燥しすぎてしまった場合でも、梅酢に浸すことで水分を補い、柔らかな食感に仕上げることができます。
また、赤シソは生の状態、もしくは軽く絞っただけのものを使用すると、より柔らかな仕上がりになります。
保存方法③:みずみずしさを保つ
この方法は、みずみずしく鮮やかな色の梅干しを好む方に適しています。
【やり方】
- 梅干しを乾燥させた後、何も入れていない保存容器に移す
- 梅干しの間に赤シソを入れる
- 容器に梅酢を注ぐ
- 容器の蓋をきちんと閉じて密封する
梅酢に浸すことで梅干しは鮮やかな色合いとみずみずしい食感を保つことができます。
ただし、この方法は酸味が強くなる傾向があるので、好みにより調整してください。
梅干し保存のおすすめ容器

多くの方が梅干しを漬ける際に使用した容器をそのまま保存用に使っていますが、より使い勝手の良いサイズの容器に移し替えると便利です。
梅干しの保存に適した容器を選ぶ際には、以下のポイントを意識しましょう。
- しっかりと密封できること
- 口が広いこと
- 食品保存用の素材でできていること
梅干しを乾燥から守るためには、密封性が重要です。
梅干しを長期間新鮮に保つための最適な保存容器を選びましょう!
以下では、自家製の梅干しを保存するのに最適な3つの種類の容器についておすすめします。
それぞれの特長や注意点を詳しく解説していくので、参考にしてみてください。
陶製の壷(つぼ)
塩分や酸に対する耐性が高く、中の温度を安定させることができます。
また、陶製なので傷がつきにくく水をはじきやすい特性があります。
口が大きく作られているので、中身を出し入れする際にも便利です。
古くから梅干しの保存に使用されている陶製の壷は、その耐久性と機能性から非常におすすめですが、その重さと持ち運びの難しさを考慮する必要があります。
ホーロー製の容器
酸や塩に強く、中の梅干しを清潔に保つことができます。
また、においが移りにくいのも大きなメリットです。
梅干しを保存するのにホーロー製の容器は非常に適しています。
においが移りにくく、清潔に保つことができますが、表面の傷には注意が必要です。
ガラス製のビン
透明なので中の状態が一目で分かり、デザイン性に富んでいる商品も多いです。
酸や塩に強く、においが移りにくい特性もあります。
ただ、光に弱いので、保存する際には日光を避ける必要があります。
中身が見えるガラス製のビンは、梅干しの状態を簡単にチェックできるので安心です。
しかし、光の影響を受けやすいので、保存場所には注意が必要です。
梅干しの保存に不向きな容器
金属製やプラスチック製の容器は避けましょう。
特に金属製の容器は、梅干しの酸によって劣化しやすいです。
プラスチック製のタッパーも酸や塩に強いわけではないので、梅干しを入れて長期間保存するのはおすすめできません。
少量ずつ入れて、短期間で食べきるようにしましょう。
梅干しは干した後の保存方法が大切 まとめ
梅干し作りは時間と労力を要しますが、成功した際の充実感は格別です。
梅に愛情を込めて丁寧に作業をすることで、日々の生活がより充実したものと感じられることでしょう。
家族が喜んで梅干しを食べてくれる姿を見ると、その苦労も報われる瞬間なので、ぜひ手作りしてみてください。
最後までお読みいただきありがとうございました!