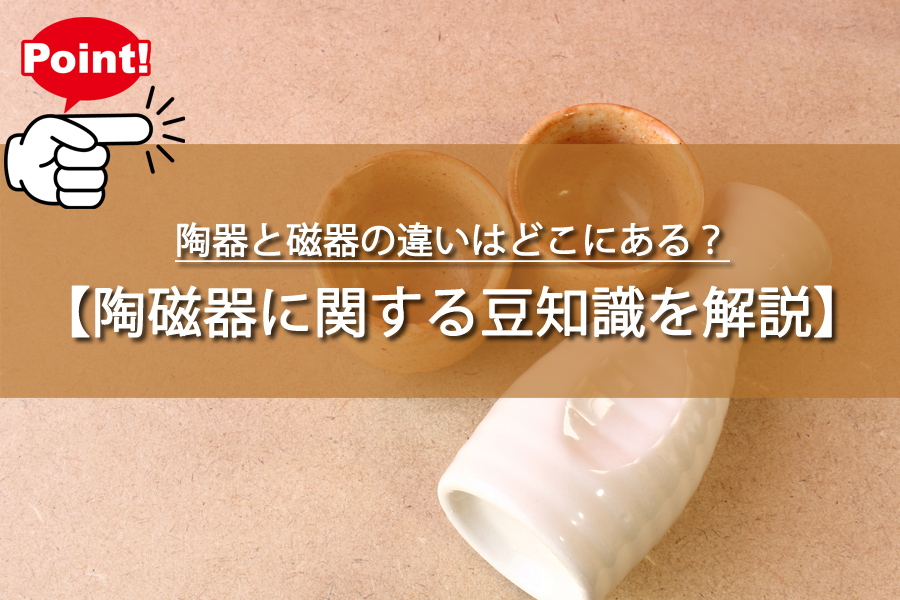陶磁器で陶器と磁器があるけど、違いってなんだろ?
素人目には、どっちも同じに見えるんだよね。

大きな違いは使われる原料にあるらしいわ。
今回は、陶磁器の豆知識ということで、陶器と磁器の違いなど紹介するわ!
「陶磁器」は、「陶器」と「磁器」の総称で、陶器と磁器という二つの異なる焼き物を含む言葉です。
今回は、これらの違いについて詳しく説明します。
「陶器」と「磁器」の主な違い

まず、「陶器」と「磁器」の主な違いは、それぞれの原料です。
陶器とは?
陶器は「土物」とも呼ばれ、主な原料は粘土で、耐久性を高めるために珪石と長石が混ざります。
焼成温度は1000℃を超え、土の成分が50%以上を占めます。
陶器は手触りが柔らかく、光を透過しないため色味は淡いです。
磁器とは?
「磁器」は「石物」とも呼ばれ、主な原料は陶石(磁石)を粉砕した石粉です。
吸水性がほぼ0%で、非常に耐久性が高く、焼成温度は高めです。
石の成分が最も多く、光を透過するため、磁器は純白色が一般的です。
陶磁器とは?
「陶磁器」という言葉は、これらの異なる性質を持つ陶器と磁器の他に、「土器」と「炻器」と呼ばれる焼き物も含みます。
土器は土を焼き固めた素焼きの焼き物で、陶磁器の前身とされています。
炻器は半磁器または焼締めとも呼ばれ、陶器と磁器の中間的な性質を持つ焼き物です。
陶磁器に関するよくある疑問

陶芸に関する知識を、以下のQ&A形式でまとめてみました。
- Q粘土はなぜ形を変えられるのですか?
- A
粘土は外から力を加えると変形し、そのままの形を保持できる可塑性を持っています。
粘土は小さな板状の結晶が積み重なった構造を持ち、水の存在によって形を変えられるのです。
- Q粘土はどうやってできるのですか?
- A
粘土は元々は石から形成されます。
長い年月をかけて風化、浸食、運搬、堆積、隆起などの過程を経て、粘土となります。
一次粘土は石が風化・浸食して粘土に変わる場合で、二次粘土は流れて池や湖に堆積してできる場合です。
- Qなぜ粘土は焼くと固くなるのですか?
- A
粘土はもともと石の成分と似ており、焼成によって固くなります。
焼き物は地中の圧力や地熱によって形成される石と似たプロセスを経ており、粘土も同じように焼くことで堅牢になります。
- Q陶器と磁器の違いは何ですか?
- A
陶器と磁器は原料、焼成温度、色、釉薬、吸水性、透光性などの違いで分類されます。
一般的に、陶器は粘土を使用し、磁器は石を粉砕して使用します。
磁器は高温(1300℃以上)で焼かれ、吸水性がなく、透光性があります。
一方、陶器は低温(1200℃~1300℃)で焼かれ、吸水性があり、透光性がありません。
- Q素焼きと焼締の違いは何ですか?
- A
素焼きと焼締は両方とも釉薬を使用しない焼き物ですが、焼成温度やプロセスが異なります。
素焼きは750℃~850℃の低温で焼かれ、釉薬を塗りやすくし欠損を防ぐための前段階焼成を指します。
焼締は釉薬を使わずに高温(1200℃~1300℃以上)で焼かれた焼き物を指します。
- Q陶器のつくり方はどんな種類があるのですか?
- A
陶器のつくり方には複数の方法があります。
主な種類には、手びねり、電動ロクロ・蹴ロクロ・手ロクロ、タタラ作り(板作り)、彫り成形(くりぬき)、型起こしなどがあります。
作成したいものの形に応じて適した技法を選ぶことが重要です。
- Q釉薬(ゆうやく)とは何ですか?
- A
釉薬は陶磁器の表面に塗るガラスのような物質です。
釉薬の主な効果には、水漏れ防止、強度向上、装飾があります。
釉薬にはさまざまな色があり、陶磁器に色と輝きを与える役割を果たします。
陶器と磁器の大きな違いは原料にある まとめ
それでは「陶器と磁器の異なる特性」に焦点を当ててご紹介しました。
陶器と磁器の最も顕著な違いは、それぞれの「原材料」に起因しています。
陶器は一般的に「土」を主要な原料とし、磁器は主に「石」を用います。
この原材料の違いにより、見た目、触感、断熱性、耐久性などが異なります。
例えば、食器を考える際、和食器は陶器が多く使用され、一方、洋食器は主に磁器が利用されています。
和食器と洋食器の違いを考えることで、陶器と磁器の違いも比較的理解しやすくなるでしょう。
最後までお読みいただきありがとうございました!