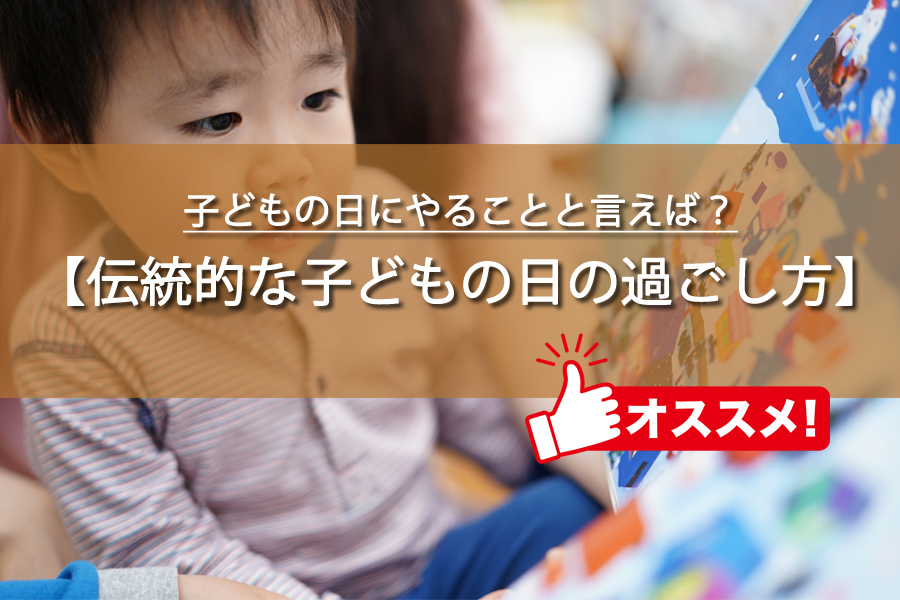子供の日にやることと言えば、パーティーくらいしか思い浮かばないけど。
昔の人はどんな過ごし方をしていたんだろ?

子供の日は伝統的な過ごし方もあるみたいね。
今回は、子どもの日にやることを、伝統的な過ごし方にヒントを得て紹介するわ!
子供の日にやることというと、具体的に何をしたらいいかで迷うこともありますが、そんなときには伝統的な過ごし方も知っておくと便利です。
今回は、子どもの日にやることを伝統的な過ごし方をヒントにご紹介します!
子供の日にやることと言えば?

子供の日にやることと言えば、やはり鯉のぼりを飾る、五月人形を飾る、柏餅を食べるなどが人気の過ごし方ですよね。
子供の日にやることの定番でもありますが、鯉のぼりをあげたり、鎧や兜などを飾ったり、柏餅やちまきを食べたり、菖蒲湯につかったりなど、意外とやることは多くあります。
ほとんどのやることが昔から伝わる風習がベースとなっているので、以下に、子どもの日にやることの定番とそれらの意味などご紹介します。
やること①ちまきや柏餅を食べる
子供の日には行事食を食べるのも昔から伝わっている風習の1つです。
ちなみに、子供の日に食べるちまきや柏餅にはちゃんと意味があります。
たとえば、ちまきは、餅米を笹の葉や竹の皮で包んで蒸した料理ですが、古代中国ではちまきが「無病息災」を願う縁起物であったことに由来し、日本でも取り入れられました。
一方、柏餅は。柏の木が新芽が出るまで葉が落ちないとの性質があることから、「家系が途絶えずに続きますように」との意味が込められています。
やること②菖蒲湯に入る
菖蒲湯は、菖蒲の葉を入れたお風呂に浸かる風習を指し、強い香りが特徴でもある菖蒲が、古代中国では邪気を祓うものとして珍重されていたことに由来します。
また、武道を重んじる「尚武(菖蒲)」と同じ音で読むことから、子どもが将来出世しますようにとの願いも込められています。
やること③五月人形を飾る
子供の日の定番飾りでもある「五月人形」は、別名「内飾り」とも呼ばれ、名前の通りに家の中に飾るものです。
この五月人形は、大きく分けて「兜飾」「鎧飾」「大将飾」の3つがあり、「子どもが強くたくましく育つように」との願いが込められています。
やること④鯉のぼりを飾る
子供の日に外に飾る鯉のぼりには、古代中国で立身出世を果たした鯉にちなんで作られたもので、子どもの将来の活躍を祈願して飾ります。
五月人形が内飾りと言うのに対し、鯉のぼりは「外飾り」と呼ばれ、基本的には家の外に飾りますが、昨今では、コンパクトな鯉のぼりもあり、家の中に五月人形などと一緒に飾れるものも多くなっています。
やること⑤折り紙で兜を作ってみる
子供の日に飾る兜ですが、よりご利益を得たいなら、折り紙などを利用して自作してみるのもおすすめです。
私が子どもの頃は、親が折り方を教えてくれて、家族皆で折り紙を楽しみました。
兜は高級品でもあるので、もし金銭的に余裕がないご家庭は、折り紙の兜でもご利益は同じです。
折り方がわからなくても、今はYOUTUBEなどの動画で折り方が配信されているので、動画を見ながら親子で仲良く作るのも素敵だと思います。
お金をかければいいと言うものでもないですし、ただ飾るよりも自作した方がより良い思い出になるかもしれません。
子供の日にやることは意外と多い まとめ
それでは、子供の日にやることを伝統的な過ごし方をヒントに、5選してご紹介してみました。
子供の日と言うと、やることは意外と多く、どれにもちゃんと意味があるので、伝統的な過ごし方をしても良いですし、現代的にアレンジしても良いですし、とにかく、子どもの将来を考えてあげることが大切です。
伝統的な過ごし方も昨今では人気があるので、ぜひ、どれか一つではなく、全部網羅するつもりでやることを決めれば、だらだらと過ごすこともないのでおすすめです。
最後までお読みいただきありがとうございました!