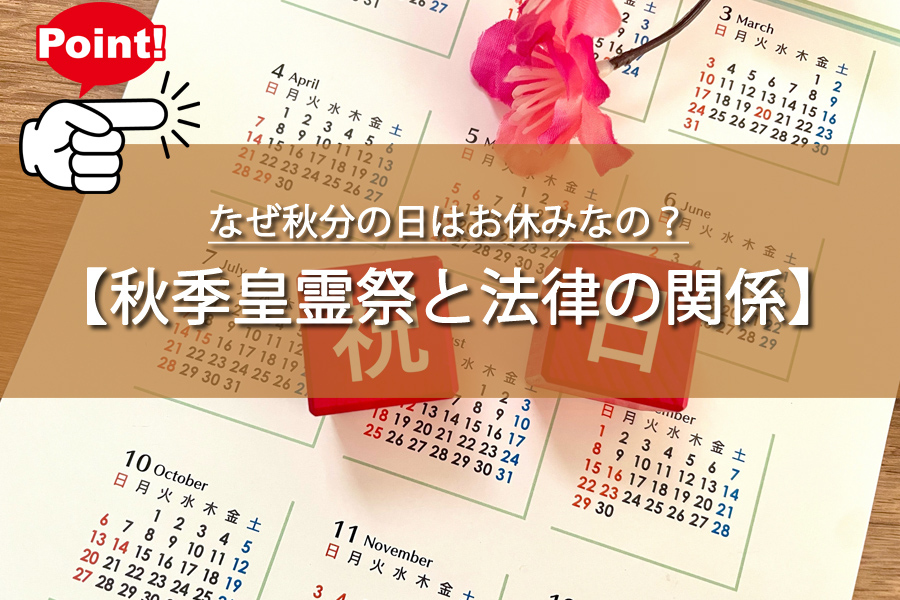秋分の日は国民の休日として休みになるよね。
でも、同じに見える夏至や冬至が休みにならないのは、なぜなんだろう?

昔から行われている秋季皇霊祭が元になってるみたいよ?
今回は、秋分の日がなぜ休みになるのかや夏至や冬至が休みにならない理由など紹介するわ!
毎年秋分の日は休みになりますが、春分の日も休みになるのに、夏至や冬至が休みにならない理由はなぜだろう?と思ったことはありませんか?
今回は、秋分の日がなぜ休みになるのかや夏至や冬至が休みにならない理由などご紹介します!
秋分の日はなぜ休みになるの?

秋分の日は春分の日と同じで、国民の休日とされ、お休みを取れる企業も多いです。
ただ、ここで疑問なのは、同じように見える夏至や冬至が休みにならないのに、なぜ、秋分の日や春分の日が休みになるのだろう?と疑問に思ったことはありませんか?
実は、秋分の日や春分の日が休みになるのは、そもそもの成り立ちが神事によるものだからです。
でも、意外かもしれないですが、そもそも昔の日本には、今のように祝祭日がなかったんです。
昔の日本には祝祭日が無かった?
日本に祝祭日が出来たのは、明治6年10月14日の「太政府官布告第334号」によって、「年中祭日祝日ノ休暇日ヲ定ム」とされたのが日本初の祝祭日でした。
その中に、春分の日の前身でもある「春季皇霊祭」もあり、もちろん、秋分の日の「秋季皇霊祭」もあります。
では、夏至と冬至はと言うと、これは祭日に指定されておらず、つまり、昔祝祭日として制定された名残が今の秋分の日がお休みになる理由となっています。
では、秋季皇霊祭とはどんな神事なのかなど、以下にご紹介します。
秋季皇霊祭とはどんな祭日?
日本で初めて祝祭日が制定されてから5年の月日が経った、明治11年6月5日のこと「太政官布告23号」で「秋季皇霊祭」という祭日が追加されました。
秋季皇霊祭とは、毎年、秋分の日に行われる、歴代の天皇・皇后・皇親の霊を祭る儀式のことで、宮内庁が毎年公開している皇室の「主要祭儀一覧」によれば「秋分の日に皇霊殿で行われるご先祖祭り」との意味合いがあるそうです。
この秋季皇霊祭が秋分の日になるきっかけは、戦後の昭和23年7月20日に「太政府官布告」に代り、「国民の祝日に関する法律」が制定されたことに影響されます。
なので、昔に祝祭日として認められていた日が新法律によって引き継がれたことで、今でも秋分の日や春分の日は国民のお休みの日とされているんです。
なぜ夏至や冬至は休みにならないの?

夏至や冬至が休みにならない理由は、お休みにする口実が何もないからと言えます。
彼岸などにも影響されず、かつ宮廷の行事などもないので、休みとする必要はないと判断されたんですね。
夏至や冬至が避けられているわけではなく、思い当る行事がなかったからというのが本当の所かもしれません。
また、行事があったとしても七夕の日や他宗教のクリスマスなどがお休みの日にならないのも、昔に主だった行事が無かったこと、また法律では祝祭日とされていなかっただけとも言えます。
決して、夏至と冬至だけが仲間外れにされているわけではないんです。
秋分の日がなぜ休みになったのかは祭事による まとめ
それでは、秋分の日がなぜ休みになったのかの理由や夏至や冬至が休みにならない理由などご紹介してみました。
秋分の日も春分の日も休みになったのは、過去に行われていた神事と法律に由来していて、伝統を残す意味で、お休みになったということかもしれません。
夏至や冬至が休みにならないのは、特に行事がないからですが、七夕のように行事があってもお休みにならない日はたくさんあります。
ただ、秋分の日がなぜ休みになったのかを知っておけば、それだけ日本文化にも詳しくなれると思うので、ぜひサイトの記事も参考にしてみてください。
最後までお読みいただきありがとうございました!