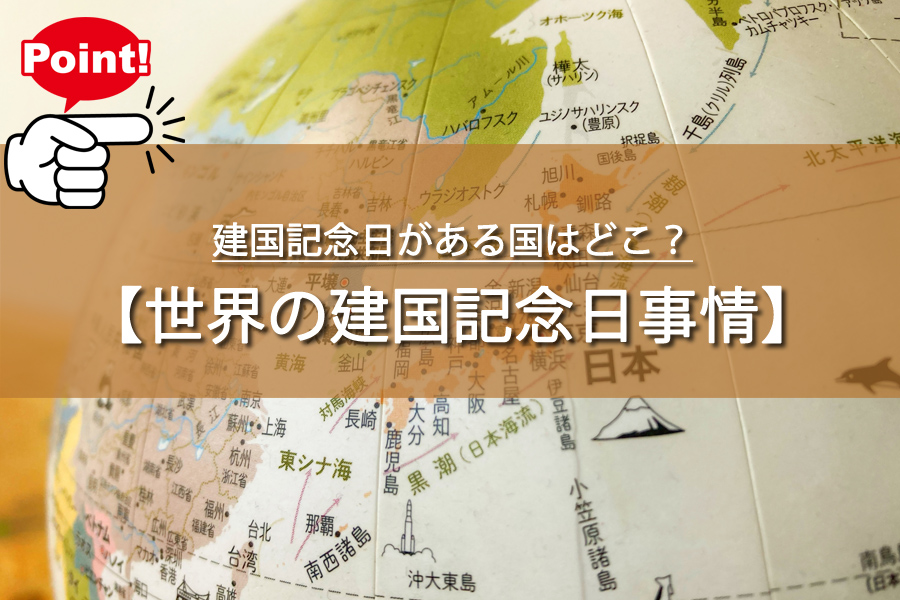日本以外にも建国記念日がある国があるらしいね。
世界の建国記念の日について知りたいな。

建国記念日は、もちろん世界にもあるわ。
今回は、建国記念日がある国はどこかを紹介するわね!
世界は多様な国々で構成され、現在196の独立国が存在するとされています。
これらの国々にはそれぞれ独自の「国民の祝日」が設けられており、今日はその中から特定の国々の記念日に焦点を当ててみたいと思います。
世界の建国記念の日

建国記念の日は、日本だけではなく、世界各国にありますが、その一部を以下にご紹介します。
オーストラリア
オーストラリアでは毎年1月26日をオーストラリアン・デーとして祝います。
これは厳密には建国の日ではなく、イギリスの植民地団がオーストラリアに初めて到達した日を記念しています。
しかし現在は、国全体で祝日として受け入れられ、家族や友人と一緒にバーベキューやピクニック、海辺で過ごすのが一般的です。
カナダ
カナダでは7月1日がカナダ・デーとして祝われており、これはイギリスからの自治権獲得を記念する日です。
全国でパレードやコンサート、花火などが行われ、国旗を身に着けた人々が共に祝賀します。
ニュージーランド
ニュージーランドでは2月6日をワイタンギ・デーとしています。
この日はイギリス政府とマオリの首長が武力衝突を終わらせるためにワイタンギ条約を締結した日ですが、言語の誤解から後に紛争が発生しました。
現在、この日は商業的なセールや各都市でのイベントで楽しまれています。
アメリカ
アメリカ合衆国では7月4日が独立記念日として知られ、イギリスからの独立を祝います。
華やかな花火やパレードが特徴で、ワシントンD.C.では国内外から多くの観光客を集める大規模なパレードが行われます。
イギリス
イギリスは、建国記念日として特定された日を持っていません。
これらの国々には様々な歴史があり、それぞれの国民の祝日には独特の物語があります。
日本の建国記念日の雑学

「日本の建国の日」について問われると、即座にその日付を答えられる人と、そうでない人がいることでしょう。
また、その日の意義について深く知っている人は少なく、多くの人がその背後にある歴史の詳細を説明するのに難渋するかもしれません。
実際、日本が国として成立した記念日は、毎年2月11日に祝われます。
この日はもともと、明治時代に制定された大日本帝国憲法の公布を記念するものであり、さらには日本の歴史において初代天皇が即位したとされる紀元前660年の出来事を、明治維新後の暦に合わせて記念する「紀元節」として定められました。
第二次世界大戦後の連合国軍の占領期に一時的にその意義を失いましたが、1967年に再び国民の祝日として復活しました。これにより、日本の建国記念日はその成立と意味において実に多面的なものとなっています。
建国を称える日の背景と重要性
建国を称える日は日本における重要な祭日ですが、他の多くの休日と異なり、その設定はやや遅れて行われました。
この祭日の起源とその意味を詳しく見ていきましょう。
祭日の成り立ち 1948年、戦後の混乱を経て、「国民の祝日に関する法律」が施行され、休日の名称や日付、そしてそれらが持つ意味が法律で決定されました。
建国記念の日の意図
国民の祝日としてのこの日は、国の成立を記憶し、国への愛着を深めるという大切な役割を持っています。
法律では、国民がこの日を通じて日本という国に対する一層の親近感を育むべきだとされています。
しかし、当初の法律では、建国を称える日がいつであるかの明確な記載はなかったため、後にこの問題が解決されることになります。
祝日の変遷
日本では、神話に登場する神武天皇が即位し、国が統一されたことを記念して「紀元節」として祝日が設けられていました。
この祝日は、天照大神の末裔とされる神武天皇の即位を祝うものでした。
しかし、戦後の連合国軍主導の占領期には、日本の象徴である天皇を中心とした祭日は廃止されました。
その後、国民からの強い要望を受け、建国を称える日が再検討され、1966年に政令が制定され、2月11日が新たな祭日として定められました。
記念の日の名称
伝承によれば、神武天皇の即位は西暦前660年のこととされていますが、旧暦と新暦の違いにより、現代の暦で見ると2月11日に相当します。
しかし、歴史学者の間では、その正確な日付や神武天皇の存在自体について意見が分かれているため、厳密な「記念日」としてではなく、あくまでも「記念の日」として位置づけられているのです。
建国記念日がある国は意外と多い まとめ
世界各地には、さまざまな形で建国の記念日が存在します。
建国記念日や独立記念日は、歴史的には悲壮な出来事や複雑な背景を持つことが少なくありません。
しかし現代では、多くの国々でその日を祝うお祭りとして楽しんでいます。
そのような記念日にあたる際には、「郷に入っては郷に従え」の精神で、現地の人々と敬意を表しながら、そのお祝いに共に参加して盛り上がることをおすすめします。
最後までお読みいただきありがとうございました!