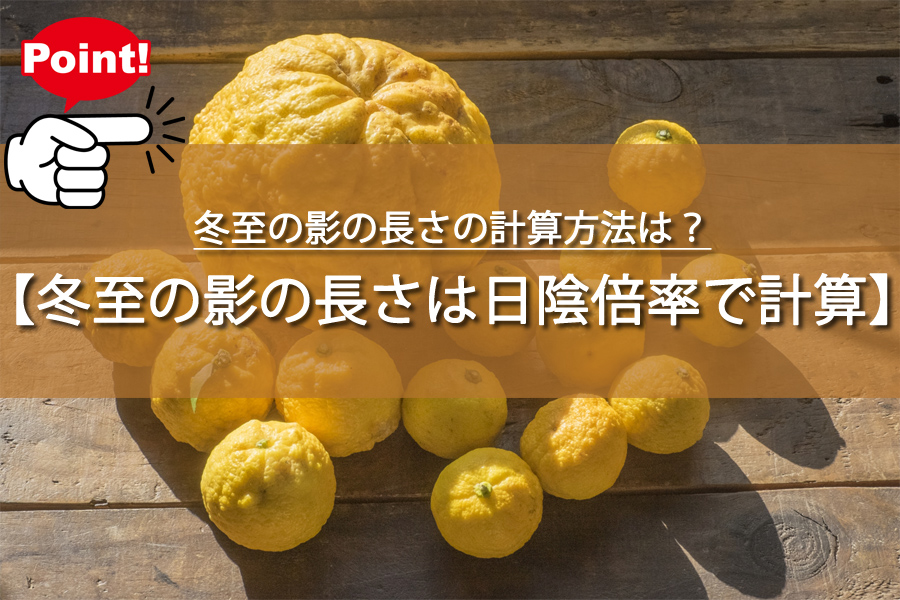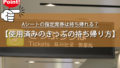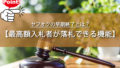冬至の影の長さってどうやって計算するんだろ?
日影の長さを求める倍率もあるって聞いたけど。

家を建てる時などに日陰倍率がわかると住みやすい家かもはっきりするらしいわ。
今回は、冬至の影の長さの計算方法や夏至との影の長さの比較を紹介するわね!
冬至は、南回帰線の上を太陽が通過する日とされていますが、影の長さを知っておかないと、日当たりの悪い部屋に当たってしまうこともあります。
今回は、冬至の影の長さの計算方法や夏至との比較、日陰倍率などについてご紹介します!
冬至の影の長さの計算方法は?

冬至の影の長さを計算するなら「影の長さ=建物の高さ × 倍率」の計算式を使います。
影の長さを知るには、三角形の一辺を数式で算出する計算式が使われますが、例えば、45度の高さに太陽があると仮定するなら「高さ」と「長さ」は二等辺三角形の短い2辺になります。
「高さ」=「影の長さ」となり、倍率は1.0となる計算です。
もっと詳しく日影の長さを求める倍率とすれば、冬至と夏至の計算式は以下のようになります。
- 冬至:1.694× 建物の高さ=影の長さ
- 夏至:0.223× 建物の高さ=影の長さ
このように計算できるため、仮に、一般的な2階建住宅なら、屋根のトップで約8m、軒の高さで約6mとなりますから、計算してみると、以下の数値になるでしょう。
つまり、1.694×8m=13.55mとなるとしたら、8mの高さで出来る影の長さは、冬至の一番陽の高い昼では13.55mとなり、庭先が5mしかない場合は、日当たりが確保できないレベルと言うことです。
日陰倍率とは何?
日陰の長さを求める時の計算に倍率を使うと書きましたが、倍率が小さければ影は短くなりますし、逆に倍率が大きくなれば影は長くなります。
つまり、上記でも軽くご紹介しましたが、日本での標準的な日陰倍率は、冬至の正午で1.694、夏至の正午なら0.223となり、計算の時にも使われます。
太陽は東から上り西に沈むことから考えると、太陽は東から西へ高度を上げながら、陽射しを投げかけてくるので、自分の家と日照を遮りそうな建物との位置関係などにも、日当たりが大きく影響しているわけですね。
日陰倍率が重要な理由
新しい家を建てる時や新しくマンションなどを借りる時、日当たりの良さは重要な項目です。
そんな時にこそ知っておきたいのが日陰倍率で、自分の住まいがある建物の位置などの日影の長さを計算できるため、計算式は覚えておくと便利かもしれません。
建物の高さを規制する「日影規制」について知りたい!
「日影規制」は建築基準法の規定で定められたものの1つですが、簡単に言えば「住宅地における中高層建築物の高さを規制することで、周辺にできる日影の時間を一定限度以下に制限する」ための規制です。
つまり「隣に高い建物ができたせいで、一日中、日光が当たらなくなった」などの被害を防ぐ目的で定められた規制です。
ただ、日影時間の制限は、季候、風土、土地利用状況などが考えられていますが、商業地域、工業地域、工業専用地域などは、日影規制の適用がされません。
とはいえ、影が用途地域を越え。規制対象区域にまで伸びるような場合は規制の対象となるので、日当たりを考えた場合、日影規制があることは知っておいた方が良いかもしれません。
マンション建設なら「日影規制」もクリア?
近隣で工事がある場合「どんな配置で、何mくらいの建物が建つんだろう?」と気になったら、自治体の管轄部署に行き「建築計画概要書」を見ておくのをおすすめします。
地域によっては、「冬至日時刻日影図」と呼ばれる図面を元にして、周辺住民への建設説明会が行われるケースもあります。
自分の家に日差しがどれくらい当たるかが気になったら、ぜひ日影規制についても注意してみてください。
冬至の影の長さの計算は日陰倍率が参考になる まとめ
それでは、冬至の影の長さの計算方法や夏至の影の長さの計算方法、日陰倍率などについてご紹介してみました。
昨今では、高い建物が近くにあるせいで日照時間なども問題となっていますが、日影規制なども知っておくと、自分の家にどれだけ日光が当たるかの概算もできるため、便利です。
冬至の影の長さを知るには、日陰倍率を使って計算しますが、日当たりの良さも決める重要な要素なので、ぜひ計算方法を知っておいてください。
最後までお読みいただきありがとうございました!