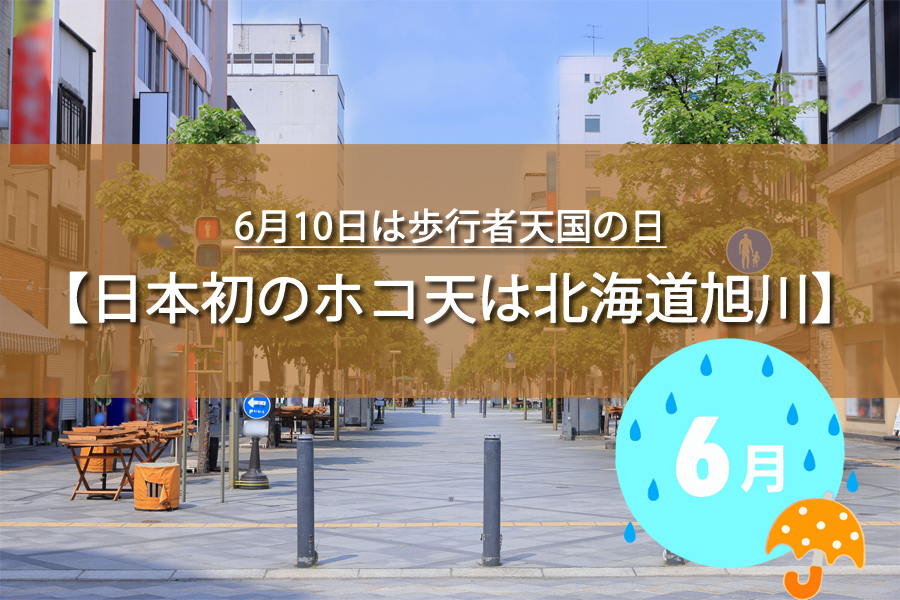6月10日は歩行者天国の日だね!
昔は良く見かけたけど、今はめったに見なくなった気がするよ。

確かに、昔は東京以外でもよく見かけたわ。
今回は、6月10日が歩行者天国の日になった由来など紹介するわね!
1973年(昭和48年)のこの日、銀座から上野までの5.5km区間で、当時世界最長となる歩行者天国が実施されました。
歩行者天国の導入は、1960年代から1970年代にかけての高度経済成長期に急増した自動車による事故や環境問題に対応するため、車優先の交通から歩行者優先の交通へと転換を求められたことがきっかけでした。
歩行者天国の特徴

歩行者天国は、道路を歩行者専用にすることで、人の流れをスムーズにし、近隣商業地の発展に寄与します。
2040年の道路の景色
2020年6月に国土交通省がまとめた「2040年、道路の景色が変わる」という提言には、「人々の幸せにつながる道路」を目指した新しい発想が示されています。
この提言のキーワードは「デジタル化」と「交流」です。
技術革新により効率的で安全、快適な道路を実現し、道路を人々が交流できる空間にすることが求められています。
歩行者天国の歴史
日本で最初の歩行者天国は、1969年(昭和44年)に旭川市の「平和通買物公園」で行われた12日間の実験でした。
この成功を受け、1970年に東京の銀座や新宿でも実施され、その後全国に広がりました。
歩行者天国の文化
1980年代には、東京の歩行者天国が若者文化の発信地となり、原宿では竹の子族やローラー族、路上バンドが集まりました。
2000年代の秋葉原では、コスプレイヤーなどが集まる場所となりました。
欧米の事例と日本の取り組み
欧州では、中心市街地の道路を完全に歩行者専用にする取り組みが進んでおり、日常の道路景色が変わりつつあります。
米国でも、道路の一部をカフェや公園として利用するパークレットが整備されています。
「2040年、道路の景色が変わる」という提言が実現し、日本中に「人々の幸せにつながる道路」が広がることを期待しています。
ホコ天の愛称で親しまれる

歩行者天国は、繁華街などの道路から一定の時間、車を締め出し、歩行者が自由に歩ける区域や制度のことを指します。
最初に実施されたのはアメリカ、ニューヨークのリンゼイ市長が五番街で行ったものでした。
日本では1970年(昭和45年)に東京の銀座や新宿、浅草、池袋の4か所で始まり、全国に広まりました。
しかし、次第に「車優先の社会から人間優先」という本来の目的が薄れ、1990年代半ばからは廃止や縮小の方向に進んでいます。
世界初の歩行者天国【ストロイエ】
ストロイエはデンマーク語で「歩くこと」を意味し、コペンハーゲン市街を東西に貫く通りを指します。
市庁舎から「コンゲンス・ニュートーゥ」までの通りで、4つの通りと3つの広場から構成されています。
多くのショップやレストラン、カフェが立ち並び、コペンハーゲンの魅力を存分に楽しむことができます。
歩行者天国は車社会でも必要? まとめ
歩行者天国は、車を締め出し歩行者が自由に歩ける区域や制度です。
最盛期には「ホコ天」として若者文化を生み出しましたが、1990年代半ばからは廃止・縮小の方向に向かっています。
最後までお読みいただきありがとうございました!