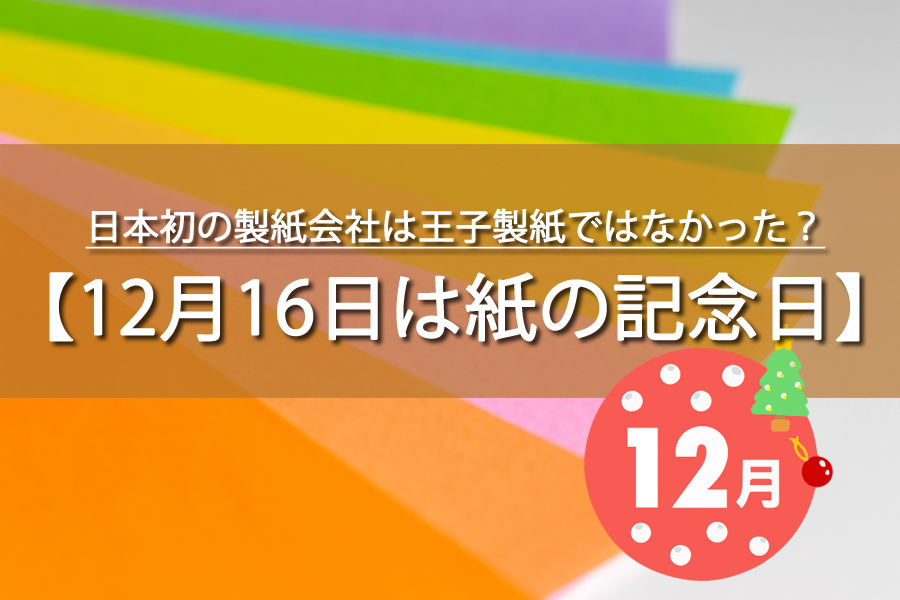12月16日は紙の記念日だね!
確か、世界初の紙は中国だったと思うけど、日本ではいつ頃できたのかな?

日本では割と遅くに紙が販売されたんじゃなかったかしら?
今回は、12月16日が紙の記念日になった由来やおもしろ雑学など紹介するわね!
12月16日は紙の記念日ですが、小学生の頃読んだ歴史漫画では、確か中国の官僚が紙を発明したとなっていたと記憶しています。
今回は、記念日ができた由来やおもしろ雑学などご紹介します!
12月16日は紙の記念日

12月16日は紙の記念日ですが、1875年に、東京の王子にある抄紙会社の工場で営業運転が開始されたことを記念して制定されました。
抄紙会社は、実業家の「渋沢栄一」が大蔵省紙幣寮から民間企業として独立させた会社で、「王子製紙」の前身にあたる企業です。
また、抄紙会社は、輸入に頼っていた当時の洋紙の国産化を企図した会社であり、明治時代に入ってからすぐの1873年には創立されました。
「有恒会社」は1872年に創立の後、1874年にはすでに操業を開始しており、日本で初の製紙会社であったのですが、株式会社になってからは「王子製紙」に吸収合併となったため、現在は会社が残っていません。
江戸時代には再生紙があった?

現代ではエコ素材として再生紙なども良く使われていますが、実は江戸時代にはすでに再生紙があったらしいです。
江戸時代の頃は、ヨーロッパでは中世時代でしたが、町中がごみに溢れ疫病も蔓延している一方で、日本ではすでにリサイクルが盛んで、街並みも諸外国と比べてもとてもきれいだったとも言われています。
そんな江戸時代に誕生した「浅草紙」は、江戸中で集めたごみの中から、紙ごみを再利用して作られた当時の再生紙でした。
作り方は、紙ごみをまず細かくしてから、釜でどろどろになるまで煮て、冷やした後は水気を切って平らにし、その後乾かすことで再生紙にしていたそうで、現代に繫がる部分でもあります。
現代の再生紙はエコとは言えない?

現代の再生紙はエコの代名詞として扱われていますが、実はそれほどエコとは言えないんです。
なぜかと言えば、資源は確かにリサイクルできるものの、再生紙を作る上でコストが割とかかってしまうからです。
なので、コストだけを見れば、再生紙を使うよりも新しく紙を作り出した方が安く済むというジレンマが起こっており、再生紙のコストが下がるような発明がなければ、もしかすると、将来的にはリサイクルもスムーズにいかないのかもしれませんね。
12月16日の出来事一覧
12月16日は紙の記念日ですが、過去の12月16日に起きたできごとなどを一覧でまとめてみましたので、参考にしてみてください。
12月16日が誕生日の芸能人は誰?
- 真山 りか(まやま りか):1996年12月16日生まれ。日本のタレント。
「私立恵比寿中学」のメンバー。 - 桐谷 美玲(きりたに みれい):1989年12月16日生まれ。日本のタレント。
2006年2月に公開された映画「春の居場所」でデビュー。 - 柄本 佑(えもと たすく):1986年12月16日生まれ。日本の俳優。
映画「美しい夏キリシマ」のオーデションに合格後、同作の主人公康夫役でデビュー。
紙の記念日には大切に紙を使ってみよう まとめ
それでは、12月16日が紙の記念日になった由来やちょっとおもしろい雑学などご紹介してみました。
日本初の製紙会社は実は「王子製紙」ではなく、有恒会社でしたが、その後吸収合併されて、王子製紙が大企業にと成長したみたいですね。
エコが叫ばれる昨今、再生紙も注目を浴びていますが、新しい紙を作るよりもコストがかかる問題もあり、そうなると、やはり本当のエコは紙を無駄遣いしないことかもしれません。
最後までお読みいただきありがとうございました!