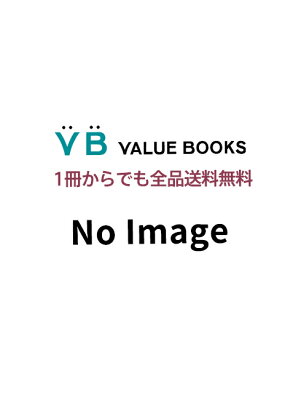6月2日は横浜カレー記念日だね!
僕はチキンカレーでもポークでも何でも好きなんだ。

甘口のカレーなら、子供も気にせず食べられるわよね。
今回は、6月2日が横浜カレー記念日になった由来など紹介するわ!
6月2日は「横浜カレー記念日」とされています。
この記念日は、1859年(安政6年)の横浜港開港と共にカレーが日本に入ってきたとされる説に基づき、横濱カレーミュージアムが制定しました。
横浜カレー記念日(6月2日)

横濱カレーミュージアムが制定したこの記念日は、1859年に横浜港が開港した際にカレーも日本に伝わったとの説に基づいています。
また、6月2日は「横浜港開港記念日」と「長崎港開港記念日」でもあります。
横浜は現在でもカレーが人気で、多くのカレー店が軒を連ねています。
老舗のカレーからスパイスカレー、インドカレー、スープカレーまで、さまざまな種類のカレーを楽しむことができます。
横浜カレーの魅力
横浜カレーを手軽に味わいたいなら「エバラ 横濱舶来亭カレーフレークこだわりの中辛」がおすすめです。
溶けやすいフレークタイプのカレールウで、ソテーオニオンなどの野菜に果実をブレンドし、20種類以上のスパイス&ハーブを使用しています。
香りと辛味のバランスが絶妙で、深いコクが特徴です。
横濱カレーミュージアム
横濱カレーミュージアムは、2001年1月26日に横浜にオープンしたフードテーマパークで、全国の個性的なカレー店が集結していました。
2007年3月31日に閉館しましたが、多くの人々に親しまれました。
今日のおすすめ本:『カレー・バイブル』
今日ご紹介する本は、ナツメ出版企画株式会社が制作した『カレー・バイブル』です。
この本はカレーの種類の多さに驚かされる内容で、レシピだけでなく、スパイスやカレーに合うデザートについても詳しく掲載されています。
まるでカレーの図鑑のような一冊で、ぜひ手に取ってご覧ください。
日本のカレーの歴史と進化

日本人に愛されるカレー。
その歩みは明治時代初期から現在まで続いています。
日本独自の味付けや生活習慣から進化し、国民食として定着したカレーの歴史を探ってみましょう。
文明開化とカレーの登場
カレーが日本に初めて紹介されたのは幕末の頃です。
1871年(明治4年)、物理学者の山川健次郎がアメリカへ留学する船上でライスカレーに出会いました。
1871年には肉食の解禁も行われ、洋食専門店が次々と開業。
「ライスカレー」は人気を博し、カレーへの関心は一気に高まりました。
陸軍と札幌農学校でのカレーの普及
1873年(明治6年)、陸軍幼年学校で土曜日を「カレーの日」と定め、その後1876年に開校した札幌農学校では、クラーク博士がライスカレーを提供しました。
この時期、カレーは広く普及し始めました。
国産カレー粉の登場と普及
1905年(明治38年)、日本で初めての国産カレー粉が発売されました。
これにより、カレーは高級食から大衆食へと変わりました。
大正時代には和風のカレーやカレー南蛮がそば屋のメニューに加わり、カレーはますます親しまれるようになりました。
昭和初期のカレーパンとソーライス
1927年(昭和2年)にはカレーパンが登場。
戦時中には食糧統制により「ソーライス」という安価なメニューも登場しました。
固形カレールウの誕生
1948年(昭和23年)には全国の学校給食にカレーが導入され、1950年(昭和25年)には固形カレールウが発売されました。
これにより、カレーは家庭で手軽に作れる料理として定着しました。
インスタント食品の普及とカレー
1956年(昭和31年)以降、インスタント食品が広く受け入れられるようになり、カレーも固形ルウからインスタント食品へと進化しました。
1963年(昭和38年)には「ハウス食品」が「バーモントカレー」を発売し、子どもから大人まで楽しめるカレーが登場しました。
レトルトカレーの登場
1968年(昭和43年)、レトルトカレーが発売され、即席カレーが家庭に普及しました。
1月22日はカレーの日
1982年(昭和57年)、全国学校栄養士協議会が学校給食週間にカレーを提供することを呼びかけ、1月22日が「カレーの日」として制定されました。
カレーは日本の日常の食卓に欠かせない国民食となりました。
カレーは子供も大好き! まとめ
それでは、6月2日が横浜カレー記念日になった由来や現在のカレーができるまでの歴史をご紹介してみました。
横浜が日本のカレー発祥の地と言われていますが、カレーは年代を問わず愛されており、ライスカレーは子供の大好物なことも多いです。
ぜひ、記念日には横浜カレーの魅力も味わってみてください。
最後までお読みいただきありがとうございました!