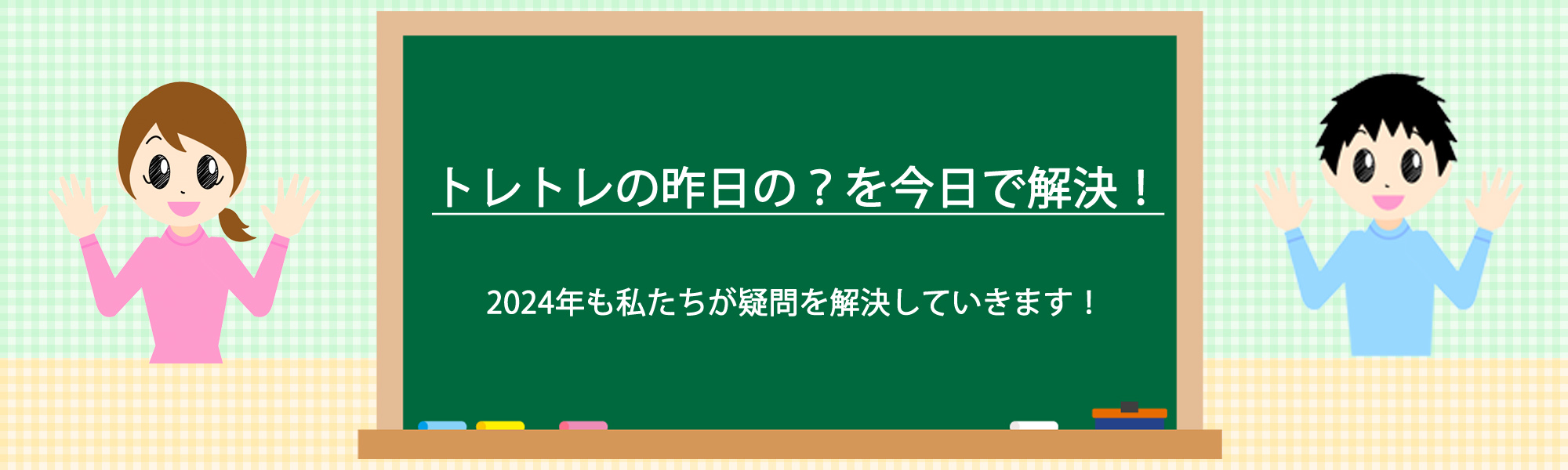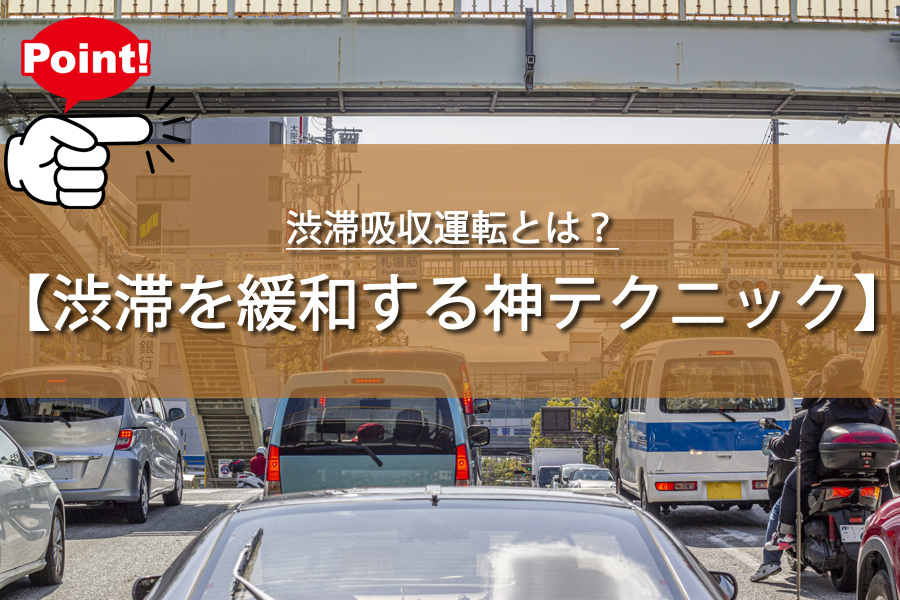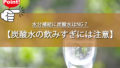渋滞とかで車間距離を空けられるとイラっとするけど…。
あれって実は渋滞を避けるテクニックの1つなんだってね。

渋滞吸収運転は、私も初耳だけど、神テクニックとも言われてるらしいわ。
今回は、渋滞吸収運転とはどんなテクニックなのかなど紹介するわね!
渋滞の時車間距離を空けて走る渋滞吸収運転ですが、実は渋滞を伸びさせないための神テクニックとも言われています。
今回は、渋滞吸収運転とはどんな運転方法なのかや、なぜテクニックが生まれたのかなどご紹介します!
渋滞吸収運転とは

渋滞を緩和させる神テクニックとも言われている「渋滞吸収運転」ですが、どのような運転なのでしょうか?
そもそも、渋滞が起きやすいのは下り坂から上り坂にさしかかる部分と言われています。
なぜ、その部分が渋滞になるかと言えば、下り坂で加速し、上り坂では減速してしまい、前の車に追いついた車が減速、続いて後ろの車も減速することが渋滞の原因だからです。
渋滞吸収運転で後続の渋滞を緩和する
渋滞吸収運転をもっと簡単に言うと、車間距離を十分に空け、流れが悪くなり、前の車がブレーキを踏んだとしても、自車はなるべくブレーキを踏まないようにするとも言い換えられます。
つまり、車間距離を多めに空けて、前を走る車の小刻みなブレーキや再加速を吸収しつつ、後に続く車の速度変化をできるだけ緩やかにするのが「渋滞吸収運転」のテクニックと言えます。
渋滞吸収運転でやっていることは3つ
渋滞吸収運転と呼ぶと、すごく難しいテクニックのようにも聞こえますが、やること自体は以下の3つだけです。
ただ、できるかできないかで渋滞の長さにもつながるので、まず渋滞吸収運転では、どんな運転をしているのかだけでも押さえておきましょう。
- 前方が渋滞したなと思ったら速度を落として、渋滞の最後尾につかないように運転する
- 車間距離を20m(高速道路の白線部分+余白1セット分)ほどに保ちながら、ゆっくりと走る
- 前方に割り込まれた場合は、さらに速度を落とし、再び車間距離を空けて運転する
高速道路では度々、大型トラックや観光バスが同じ運転をしていることがありますが、車は停止→再発進にエネルギーを使うので、それを避けるための動きとも言い換えられます。
この動きこそが渋滞吸収運転の例でもあるので、自分が運転する時にもぜひ見習ってみましょう!
車間を空けた方が良い理由

車間距離を空けることの大切さについてご紹介しましたが、車間距離の目安を考える時は、距離ではなく時間で計算してみましょう。
渋滞吸収車は、前を走る車との車間距離を十分にとることで、停止せずに走行を続けることができるのが強みです。
道路の渋滞を防ぐには、車間距離を空けない方が良いようにも思えますが、実際には車間距離を取った方がスムーズに走れるというわけですね。
むやみな車線変更は渋滞を悪化させる?
渋滞で気を付けたいのは車間距離だけではなく、車線変更にも注意が必要です。
渋滞が始まると「少しでも早く進みたい」というドライバー心理が働きますが、追越車線へ移る車両が増えれば、逆にブレーキの伝播から渋滞の発生につながる可能性もあります。
なので、混んでいる時にこそ、走行車線を走り続ける「キープレフト」も渋滞緩和には必要です。
渋滞吸収運転はやっていること自体は単純 まとめ
それでは、渋滞吸収運転とはどんなテクニックなのか、また車間距離を空ける必要性などご紹介してみました。
渋滞時に、のろのろ走ってるようにも見える渋滞吸収運転ですが、実は渋滞を緩和させる神テクニックでもあります。
車間距離を空けることこそが、渋滞が伸びないための方法です。
割り込まれるとイラっとする方も多いかもしれないですが、気にせず、車間距離を保って、他の車の渋滞を軽くしてあげてください。
最後までお読みいただきありがとうございました!