
中学校の卒業式では、答辞を聞くと皆が一斉に涙を流すんだよね。
答辞って、やっぱり心にぐっとくるものがあるね。

答辞を言ってる人も泣いちゃうのよね。
今回は、思わず泣ける答辞の書き方や例文など紹介するわ!
卒業式の答辞といえば、違う高校に旅立つ卒業生に向けての締めくくりの言葉でもありますし、思わず泣けるという方も多いんじゃないでしょうか。
今回は、思わず泣ける卒業式の答辞の書き方例などご紹介します!
思わず泣ける卒業式の答辞の書き方

卒業式の答辞で思わず泣けるシーンといえば、卒業生もそうですが、両親への感謝の気持ちを伝えた時だと思います。
そもそも家族は一緒にいるのが当たり前のように感じることも多々あり、両親から叱られると時にはうるさく感じることもあります。
そこで卒業式の答辞で、感謝の気持ちを答辞にこめると、思わず両親が泣いてしまうような文章になります。
また、卒業生もその両親への感謝の言葉が自分に重なることで、両方とも答辞で思わず泣く方も多いでしょう。
ただ、卒業式に必ず泣けるような答辞を書く必要はないので、泣くや泣かないに関わらず、最後まで読み上げることが大切です。
思わず泣ける卒業式の答辞の書き方

答辞の文章を考えるのは大変ですが、テンプレートがあるので、初めての方はまず以下のような構成にすることを心がけてみてください。
- 挨拶
- 卒業式を開催してくれたことへの感謝の言葉
- 来賓の方など出席してくれている方に対しての感謝の言
- 在学中の思い出
- 今後の決意
- 先生や親への感謝の言葉
- 締めの言葉
基本的には挨拶から始まりますが、挨拶には季節感を出すために季語を入れるのもポイントです。
たとえば「開花を待つ桜の蕾の息吹が感じられる季節~」などのように答辞が始まれば、どことなくおしゃれに感じますし、卒業式にもふさわしいですよね。
続いて「本日は、私達のために素晴らしい卒業式を挙行してくださり、誠にありがとうございます。」と挨拶を述べ、「ご出席下さいましたご来賓の皆様、また校長先生をはじめ諸先生方、並びに関係者の皆様に、卒業生一同心からお礼申し上げます。」などのように来賓の方に感謝の言葉を短く伝えます。
次に、在学中の思い出の部分では、以下にご紹介する感動するエピソードや面白いエピソードを盛り込んでみましょう。
そして、今後の決意では「この学校で学んだことを胸に、これからの人生を切り開いて参ります。」と抽象的な未来像を述べ、「最後になりましたが、今まで学校生活を支えてくださった全ての方に、改めて感謝を申し上げます。そして、これからも私達を見守り、ご指導のほどよろしくお願い申し上げます。」と感謝の気持ちを伝えます。
最後の締めの部分では「私たちの学校が、これからも素晴らしい歴史を刻んでいくことをお祈りして、答辞とさせていただきます。令和○年○月○日 卒業生代表 ○○」などのように、学校の繁栄を祈るのが一般的な締めとされます。
感動する答辞の例文
答辞で感動する文章を書きたいなら、方法としては「自分のエピソードを入れてみる」「感謝の言葉を盛り込む」「自分が努力したエピソードを入れてみる」などしてみましょう。
たとえば、自分のエピソードを入れるなら、このような例文があります。
このような感じで自分が努力した、もしくは体験したエピソードを盛り込むと、共感してくれる卒業生も多くなり、思わず泣けるような答辞になると思います。
面白い答辞の例文
答辞で面白いエピソードを盛り込むと、笑いの渦の中で、こちらもなぜか泣けるような答辞が書けると思います。
おもしろエピソードを書くなら、周りの方にも協力してもらい、泣き笑いが渦巻く卒業式にしてみましょう。
たとえば「先生にも協力してもらう」「自分自身の面白エピソードを入れる」「協力者を集めて面白くする」などの方法がありますが、先生に協力してもらうなら、こんな文章がおすすめです。
このような感じで、先生にも協力してもらうと、卒業生も懐かしさに涙が込み上げてくるかもしれませんね。
卒業式で泣けるような感動的かつ面白い答辞を書こう! まとめ
それでは、卒業式で思わず泣けるような、感動的で面白い答辞の書き方の構成や、答辞の例文などご紹介してみました。
答辞は必ず泣けるような文章にする必要はありませんが、最後の締めくくりとして、ぜひ笑いと感動の渦を巻き起こすような答辞にしたいですね。
ぜひ、例文を参考にして、思わず泣けるような感動的な答辞を述べて、卒業式を締めくくってみてください。
最後までお読みいただきありがとうございました!
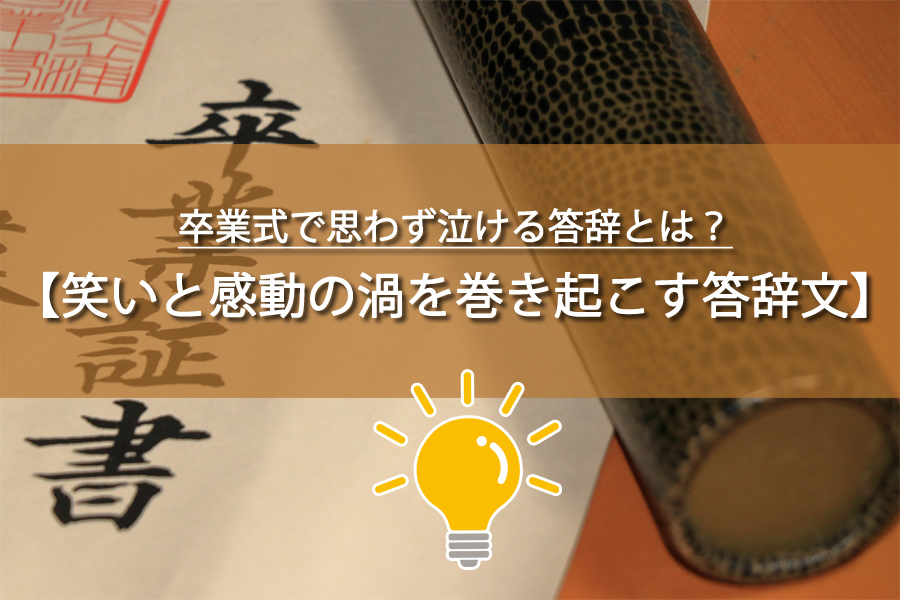


私は中学校に入学してから、小学生の時とは違い、勉強が分からない、難しいと感じ、やりたくない、勉強したくないと思ってしまいました。
しかしそれではいけないと先生に相談しながら、じっくり丁寧な指導をしていただいたり、家でも両親や兄に分からない点を聞いたりして、少しずつ理解できるようになりました。
これを繰り返しているうちに少しずつ「分からない」「嫌だ」という気持ちがなくなり、勉強を楽しめるようになり、ここまで来れました。