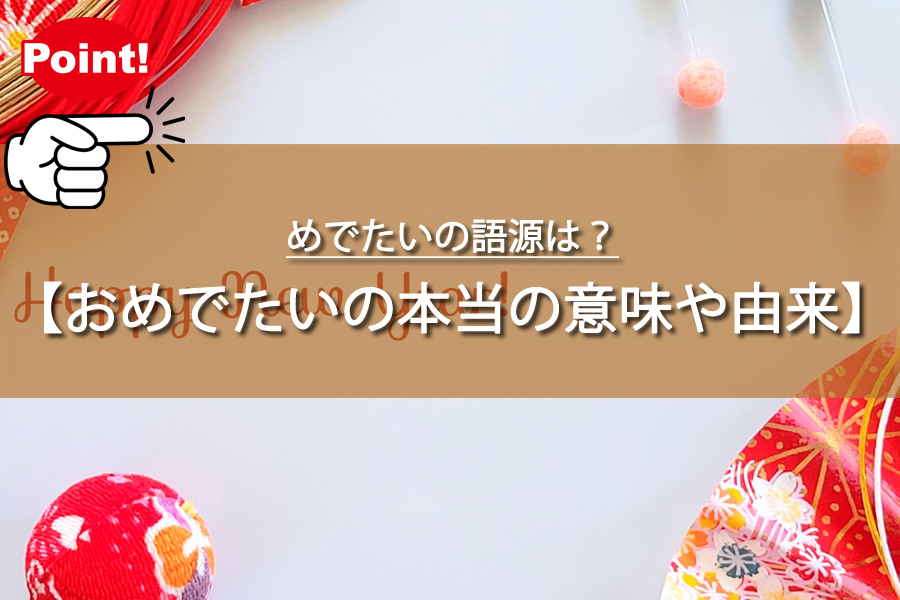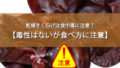お正月になるとめでたいって使うけど…
そもそもの意味や由来は何だろう?

漢字に当てはめるとちょっと驚くかも。
今回は、めでたいの語源や意味など紹介するわ!
新年や特別なお祝いごとによく耳にする「明けましておめでとう」は、新たな年が始まることを祝い、幸福を願う伝統的な挨拶です。
しかし、「おめでとう」という言葉の意味を本当に理解しているでしょうか?
今回は、この一見当たり前の挨拶に潜む意味について掘り下げてみましょう。
「めでたい」の語源は?

「目出度い」とは、その字面からして「目が出るほど」という意味合いを連想させるかもしれませんが、実際は驚きや喜びがあまりにも大きくて目を見開くような状態を表しているわけではありません。
また、「芽出度い」という表記も見られることがありますが、これもまた「新たな幸せの芽が出る」ことを願う表現であると解釈することができます。
「おめでたい」という表現の本質
「おめでたい」という言葉の本質は、「賞賛するに値するほど素晴らしい」という意味の「めでいたし」の縮約形です。
したがって、現代で使われる「おめでとう」とは、祝うに値する素晴らしい状態、特別な喜びを表す表現として用いられているのです。
あけましておめでとうの意味
まとめると、「明けましておめでとう」は、ただの形式的な挨拶ではなく、新たな年や幸せな出来事がもたらす賞賛に値する素晴らしさや喜びを表現する深い意味を持つ言葉なのです。
新年を迎える際や大切な人の幸せな瞬間にこの言葉を使うことで、共にその喜びを分かち合い、祝福する心を伝えているのです。
めでたいの本当の意味?

「明けましておめでとう」という言葉は、新年の祝福と喜びを表すフレーズとして広く使われています。
この中の「おめでとう」には実は「愛でたい」という意味が込められているという説があります。
これは美術品を鑑賞するときの「めでる」や、愛する人に対する感情など、何かを高く評価し、心から愛おしむという感情を表しています。
新年の訪れを、美しいものや大切なものとして「愛でたい」と願う心が、この言葉には込められています。
新しい年も愛情を持って、幸せに満ちた一年を迎えたいという願いと共に、この挨拶を交わし合うわけです。
鯛がめでたいとされる理由

鯛は、昔から日本で祝事に欠かせない魚とされ、その理由には多くの縁起の良い要素が含まれています。
特に、お祝いの際には鯛の姿焼きが好まれ、これは「めでたい」にちなんで「目出鯛」とも呼ばれています。
この言葉遊びは、そのまま祝福の象徴として継承されてきました。
鯛の縁起良さには、以下のような要素があります。
- 寿命の長さ: 長寿を象徴し、長生きを祈願する意味で用いられることが多いです。
- 美しい外見: 赤い体色は魔除けや生命力を象徴し、白い身は純潔や清らかさを表します。この紅白の配色は、めでたい席にふさわしい色とされています。
- 恵比須様の象徴: 商売繁盛や豊漁を祈る恵比須様が鯛を抱えている姿が知られており、これも縁起の良さに寄与しています。
- 鯛の骨: 鯛の特定の骨には、鯛の形をした「鯛の鯛」というものがあり、これもまた縁起物とされています。
- 尾頭付きの象徴性: 頭から尾まで一貫して物事を成し遂げる象徴として、尾頭付きの鯛が用いられます。
これらの理由から、特別な祝い事には鯛が用いられる伝統があり、今でも多くの人々に愛され続けています。
その美しい姿と豊かな象徴性が、祝福の席をより華やかに彩るのです。
めでたいの語源や意味を知って正しく使おう! まとめ
“めでたい”という言葉は、漢字で「目出度い」や「芽出度い」と書かれることがありますが、これらは本来の意味とは直接関係のない表記方法です。
この言葉は、本来、「賞賛すべきほどに素晴らしい」という意味を持っており、何かが「立派で」「見事である」という時に、その状況や物事を高く評価する際に使われます。
最後までお読みいただきありがとうございました!