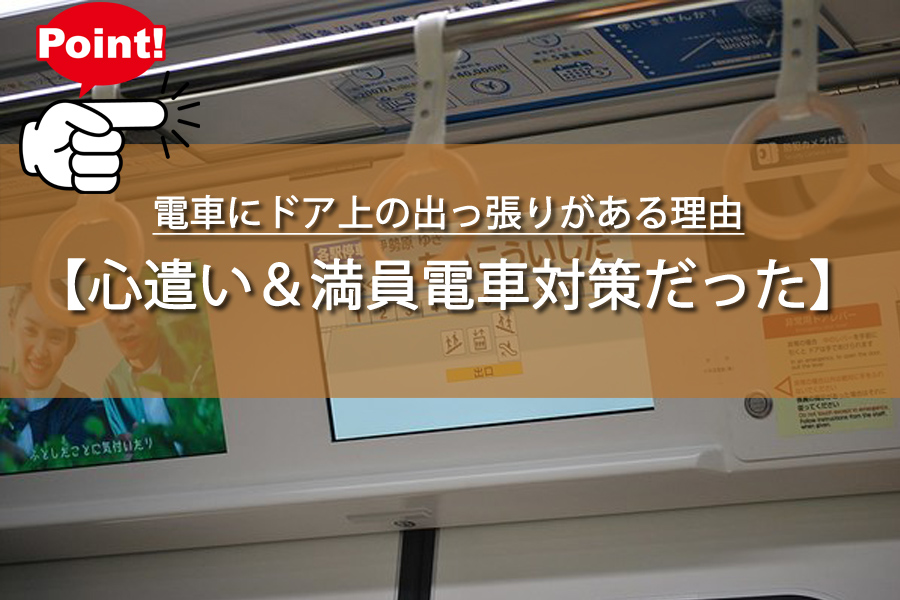最近の電車って、ドア上に出っ張りがあるけど…
あれって、何のためについてるのかな?

どうやら、製作者の心遣いらしいわ。
今回は、電車のドア上の出っ張りが増えている理由など紹介するわね!
昨今、電車の「ドア上の出っ張り」が増加中とのことですが、知らない人が見たら、何に使うんだろう?と不思議ですよね。
今回は、電車のドア上の出っ張りが増えている理由などご紹介します!
電車のドア上の出っ張りは何のためにある?

画像引用元:Yahoo!ニュース
昨今増えつつある、電車のドア上の出っ張りですが、これが設置されるようになった理由は、製作者の心遣いだそうです。
ただ、その場合、つり革も近くに無いので、発車や到着の時の加速時や、減速時に掴むためにあるのが、「ドア上の出っ張り」です。
東急の広報担当者によると「車内混雑時など、乗車の方の手掛けとして導入しています。」とのこと。
「強く握る」というよりも、あくまで「車内混雑時などに乗車する時の手がけ」として設置されており、電車の急発進などで体がよろけるのを防ぐ目的があるみたいですね。
もちろん、ドア上の出っ張りは身長がないと掴むのがそもそも難しいですが、身長がある程度ある男性のサラリーマンなどの方には嬉しい仕様となっています。
つり革さえつかめない、都市圏の電車内で、掴む場所があるのはありがたいですよね。
最近の電車のドア上部には、LCD(液晶ディスプレイ)が搭載されることも多いですが、出っ張りがあるだけで、乗車も楽になるので、ぜひ地元の電車にもつけて欲しい機能です。
出っ張りは実際に増えている?
最近の電車では、ドア上部に「LCD(液晶ディスプレイ)」が搭載されることが多いですが、一部の電車には上記でご紹介したように、出っ張りがついています。
実際に、JR東日本の主力車両の「E233系電車」はLCDの下が「つるん」としているのに対し、小田急などの「最新型5000形」では手前に飛び出した出っ張りがありますよね。
そのなかでも、東急は近年の車両(5000系、6000系、7000系、2020系列など)に出っ張りを「完備」しているそうで、他社とくらべて奥行きがあり「掴みやすい」感じです。
私が学生の頃は、出っ張りなどなく、すし詰めの状態だと本当に掴まる場所がなく大変でした。
その意味でも、出っ張りが増えれば、通勤や通学ラッシュなどでは大変助かりますよね。
つり革の両方にぶら下がって遊ぶ人を過去に見かけたことがありますが、危ないのもありますし、つり革も出っ張りもバランスを取るためにあるので、正しい使い方を心がけてみてください。
そもそも、電車のドア上の出っ張りは、奥行きが指の関節2つ分も無いため、全体重をかけるのは構造的にも想定されておらず、やらない方が良いと言うよりは出来ないと言うのが正しいかもしれません。
電車のドア上の出っ張りが嬉しいとの声も多数
電車のドア上の出っ張りに対しては、SNSでも話題になったことがあり、賛否両論あるものの、やはりあると便利という声やありがたいとの声も多数あります。
以下に、ツイッターでの口コミを見ていきましょう。
私の地元の電車にもつけて欲しい…
何のため?って疑問に感じていた方も多いみたいです。
「社畜です。」が一時期話題になりましたね。
電車のドア上の出っ張りは満員電車対策 まとめ
それでは、電車のドア上の出っ張りは何のためについているのかや出っ張りが増えている理由などご紹介してみました。
電車のドア上の出っ張りは、満員電車対策で、つり革さえつかめない時に掴める場所として設置されているようですね。
私の地元の電車にはありませんが、出っ張りがあれば、少しでも体のバランスを整えることができるので、ぜひ、設置された電車が増えてくれないかなと思います。
最後までお読みいただきありがとうございました!