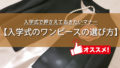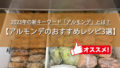1月18日は都バスの日だね!
僕はまだ乗ったことがないんだけど、一度乗ってみたいんだよなぁ。

私もバスはちょっと苦手だけど、都バスには乗ってみたいわ。
今回は、1月18日が都バスの日になった由来やおもしろ雑学など紹介するわね!
1月18日は都バスの日ですが、東京都のバスってちょっとした憧れで、田舎のバスとの違いを一度確かめてみたいなぁなんて思っています。
今回は、記念日ができた由来やおもしろ雑学などご紹介します!
1月18日は都バスの日

1月18日は都バスの日ですが、1924年に、東京市営の乗合バスの2系統(巣鴨から東京駅、中渋谷から東京駅)が営業開始となったことを記念する日です。
この時のバスは「T型フォード11人乗り」で、「円太郎」の愛称で親しまれています。
都バスの営業開始のきっかけとなったのは、1923年9月1日に発生した関東大震災の影響で、東京市が運営していた東京市電が大打撃を受けたことによるものです。
復旧には相当な期日がかかることが見込まれたこともあり、市電の代替輸送機関としての乗合バスが導入されたみたいですね。
その後復旧が進み、路面電車も動くようになったことで都バスは運航停止となる予定でしたが、すっかり交通手段として定着していたため、現在まで運行は続けられています。
路線バスにシートベルトがない理由

シートベルトの着用が義務付けられるまでは、乗用車でもバスでも特にシートベルトをつける必要はありませんでしたが、事故などが起こりやすくなった現代では、シートベルトをつけていないだけでも違反切符が切られますよね。
でも、そんな現代でも路線バスにはシートベルトがないのを不思議に思ったことはありませんか?
実は、路線バスにシートベルトがないのは、シートベルトの設置の有無が「道路運送車両の保安基準」に設けられているからで、つまり、乗車定員によって義務付けられるかどうかが決まっているんです。
路線バスの乗車定員は11名以上となるため、「道路運送車両の保安基準」の基準外となり、シートベルトの設置や着用を義務付けられていないんです。
なので、シートベルトの着用が義務付けられている昨今でも、路線バスは対象外となっています。
路線バスが定員オーバーにならない理由

普段から路線バスを利用されている方はご存じかと思いますが、通勤や通学ラッシュの時間帯には車内がぎゅうぎゅう詰めになり、すし詰め状態になりますよね。
でも、それだけの人が乗り込んでも、路線バスでは定員オーバーとなりません。
なぜなら、路線バスの定員には「サービス定員」と呼ばれる考え方が適用されており、通常の運行に支障がなければ、立って乗っている人がいたとしても、乗車できているのでOKとされているからです。
バスのサイズにもよりますが、サービス定員の場合、70~80人が定員とされており、実際にどれだけ乗客が乗ったとしても、せいぜい60人が良い所なので、最初から定員オーバーになるだけの人数が乗れないことから、路線バスには定員オーバーという概念がないんです。
1月18日の出来事一覧
1月18日は都バスの日ですが、過去の1月18日に起きたできごとなどを一覧でまとめてみましたので、参考にしてみてください。
1月18日が誕生日の芸能人は誰?
- 久保田 紗友(くぼた さゆ):2000年1月18日生まれ。日本の女優。
ドラマ「神様のイタズラ」の主演に抜擢され、同作品の主題歌も担当。 - 山崎 育三郎(やまざき いくさぶろう):1986年1月18日生まれ。日本の俳優。
「モーツァルト!」での演技により、第36回菊田一夫演劇賞・演劇賞を受賞。 - ビートたけし:1947年1月18日生まれ。日本のタレント。
明石家さんま、タモリと共に、日本の「お笑いBIG3」として知られる。
都バスに乗って市内観光してみよう! まとめ
それでは、1月18日が都バスの日になった由来やちょっとおもしろい雑学などご紹介してみました。
都バスは、震災の時の代行のような形で運営が開始されましたが、人気が根強く、路面電車と共に現在でも活動中です。
都バスに限らないですが、バスは停留所がある場所で降りられるので、駅まで行かなくて済むのが便利ですよね。
ぜひ、都バスの日には、都バスに乗って、市内観光など楽しんでみてください。
最後までお読みいただきありがとうございました!