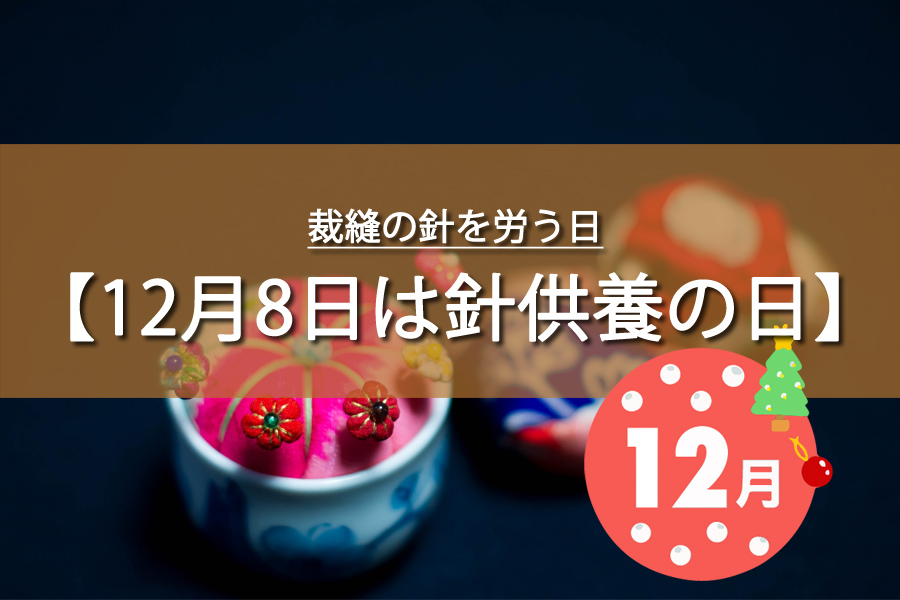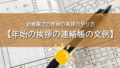12月8日は針供養の日だね!
針を供養するなんて、日本人らしい考え方って気がするよ。

何にでも神様がいる日本人独特の考え方よね。
今回は、12月8日が針供養の日になった由来やおもしろ雑学など紹介するわ!
12月8日は針供養の日ですが、折れた針や曲がった針を供養するという考え方は、日本人独特の考え方かもしれません。
今回は、記念日ができた由来やおもしろ雑学などご紹介します!
12月8日は針供養の日

12月8日は針供養の日ですが、縫い針を供養するために、2月8日と12月8日が記念日に制定されています。
針供養の日には、裁縫を休み、古い錆びた針や折れた針などの使えなくなった縫い針を集め、社寺に納める、豆腐やこんにゃくなどの柔らかいものに刺すなどして供養をするみたいですね。
淡島神社や淡島神を祀る堂がある寺院で行われることが多いですが、中でも、東京の江東区にある「浅草寺境内の淡島堂」、もしくは「和歌山県和歌山市の淡嶋神社」が有名です。
日頃から使用している針に供養をするなんて、日本人らしい考え方ですよね。
ちなみに、針供養の由来は中国の「社日に斜線(針と糸などの裁縫の仕事)を止む」との習わしから来ており、社日が「生まれた土地の守護神を守る日」とされていることから、「守護神を守る日には針仕事をやめましょう」との風習から来ています。
待ち針の語源は平安時代?

裁縫をする時、布が動かないように止めるのに待ち針を使いますが、この待ち針という名前の由来は、平安時代の小野小町から来ているそうです。
小野小町は日本の三大美女としても有名ですが、小野小町は言い寄ってくる男性をことごとくはねのけた女性でもあり、それがきっかけで、小野小町は「穴」がない女性と揶揄されます。
そこから転じて、穴のない針=小町針と呼ぶようになり、時代を変遷していく中で、小町針が「待ち針」と名を変えていったんですね。
裁縫が特技の鳥がいる?

特技がある鳥は世界中にも多くいますが、中には裁縫が得意な鳥がいるってご存じでしたか?
ただ、日本昔話にある「鶴の恩返し」のような特技が裁縫ということではなく、自分の巣を作り上げるのに裁縫の特技を用いている鳥なんです。
サイホウドリと呼ばれている鳥ですが、隣り合っている葉を選んで縫い合わせることによって、巣を作り出していると言います。
葉の縁にくちばしで穴を開けたら、その穴を蜘蛛の糸で縫い付けて巣を作り上げるなんて、人間でも驚きの離れ業ですね。
12月8日の出来事一覧
12月8日は針供養の日ですが、過去の12月8日に起きたできごとなどを一覧でまとめてみましたので、参考にしてみてください。
12月8日が誕生日の芸能人は誰?
- 安田 顕(やすだ けん):1973年12月8日生まれ。日本の俳優。
「週刊Nanだ!Canだ!」のコーナー企画でテレビ番組に初出演。 - 稲垣 吾郎(いながき ごろう):1973年12月8日生まれ。日本のタレント。
アイドルグループ「SMAP」の元メンバー。 - 大竹 一樹(おおたけ かずき):1967年12月8日生まれ。日本のお笑いタレント。
お笑いコンビ「さまぁ〜ず」のボケ担当。
裁縫で使われる針を供養する日 まとめ
それでは、12月8日が針供養の日になった由来やちょっとおもしろい雑学などご紹介してみました。
針が休めるようにと豆腐やこんにゃくに針を刺すなんて、日本人らしい労いの方法ですよね。
裁縫を仕事にしていなくても、ボタン付けなど裁縫をする方は少なからずいらっしゃると思うので、ぜひ針供養の日には、針を供養して、針をねぎらってあげてください。
最後までお読みいただきありがとうございました!