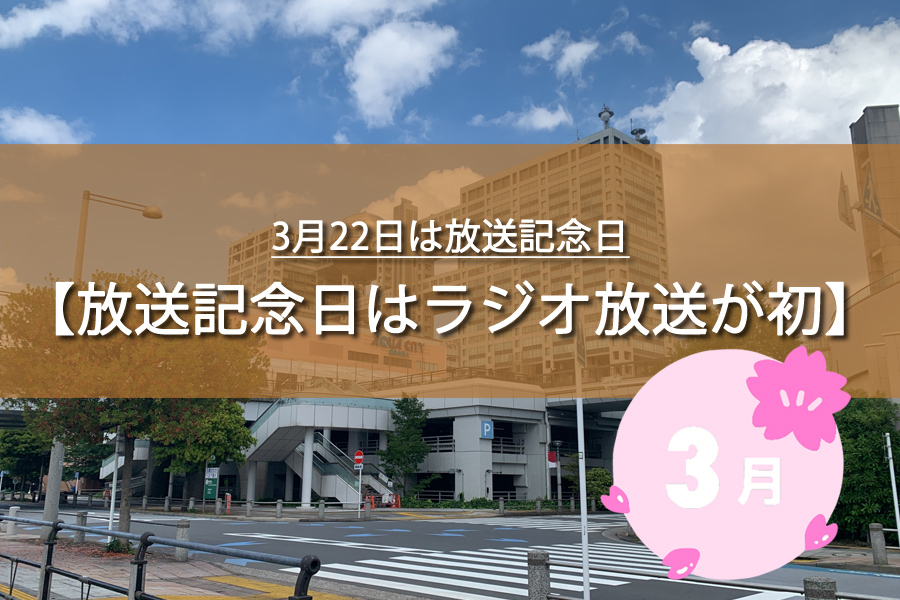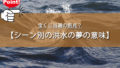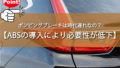3月22日は放送記念日だね!
当時は、どんな放送がされたんだろう?

最初の放送はコールサインだったみたいね。
今回は、3月22日が放送記念日になった由来など紹介するわ!
放送記念日は、毎年3月22日に祝われます。
この記念日は、日本放送協会(NHK)によって1943年(昭和18年)に設定されました。
3月22日は放送記念日

背景には、1925年(大正14年)3月22日に、当時の東京放送局(現在のNHK東京放送局)が日本で初めてのラジオのテスト放送を行った出来事があります。
このテスト放送は、東京・芝浦の東京高等工芸学校の一時的なスタジオから行われ、京田武男アナウンサーが放送開始の合図として「アー、アー、アー、聞こえますか。JOAK、JOAK、こちらは東京放送であります。こんにち只今より放送を開始致します」とアナウンスしました。
放送開始は3月1日に予定されていた?
当初の計画では、放送開始は3月1日に予定されていましたが、必要な送信機が大阪放送局に買い取られるというアクシデントがありました。
結局、東京電気研究所の送信機を借りて改造し、逓信省(現在の郵政省)の検査を経て、3月22日に仮放送を開始することになりました。
本放送は同年7月12日に開始されましたが、大阪放送局も同年6月1日からの仮放送を開始しています。
現存する最古のNHKの番組
また、現存する最古のNHKの番組映像と言われているのが、1952年(昭和27年)12月13日に放送されたドラマ『枯草物語』です。
このドラマは約4分間の映像で構成されており、当時の技術の限界から音声は含まれていません。
フィルムには、名古屋さんが追いかけられて殴られるシーンなどが収められています。
これはNHKが制作した番組としては最古の映像記録とされています。
日本テレビ放送の歴史

日本のテレビ放送自体は、NHKによって1953年2月1日に始まりました。
その後、同年8月28日には日本テレビが日本初の民間テレビ放送をスタートさせ、全国にテレビ局の設立が相次ぎました。
当時のテレビは非常に高価で、多くの家庭では手が届かないものでしたが、街頭に設置された公共のテレビが人々を惹きつけました。
テレビが家庭にも普及
日本経済が1950年代後半に急成長を遂げると、テレビは急速に家庭に普及しました。
1959年4月10日には、当時の皇太子の結婚式の生中継が大きな話題となり、テレビ受信契約数は200万台を超えるマイルストーンに達しました。
その後、1960年代に入ると、カラーテレビ放送が開始され、1964年の東京オリンピックを契機に、カラーテレビは日本中に普及しました。
1975年にはカラーテレビの普及率が90%を超え、テレビ放送は日本の家庭にとって不可欠な存在となりました。
その後も、テレビ放送技術は進化を続け、1980年代には衛星放送が、1990年代にはハイビジョン放送が、そして2003年からは地上デジタル放送がスタートしました。
最初の画像伝送装置はイギリス
一方、テレビの起源には、19世紀にさかのぼるアイデアがあります。
その後、日本では1926年に高柳健次郎がブラウン管を使用したテレビの実験に成功し、テレビ放送の基礎を築きました。
高柳の開発したテレビは、画像を電気信号に変換して送信し、ブラウン管で映像を再生する仕組みでした。
ブラウン管テレビとフェライト製品の関係
ブラウン管テレビの発展には、TDKが生産したフェライト製品が大きく貢献しました。
この技術は戦後もテレビ放送の発展に役立ち、現代のフラットテレビに至るまで、TDKの部品はテレビの進化に欠かせないものとなっています。
放送記念日はまとめ
以上で、3月22日の放送記念日にまつわるご紹介は終わりです。
最古の映像も残っているのがすごいですが、日本で初めての放送からもう90年以上が経過しているのは驚きです。
最近は若者を中心にテレビ離れが進んでいますが、時には昔の作品に触れてみるのも面白いかもしれませんね。
最後までお読みいただきありがとうございました!