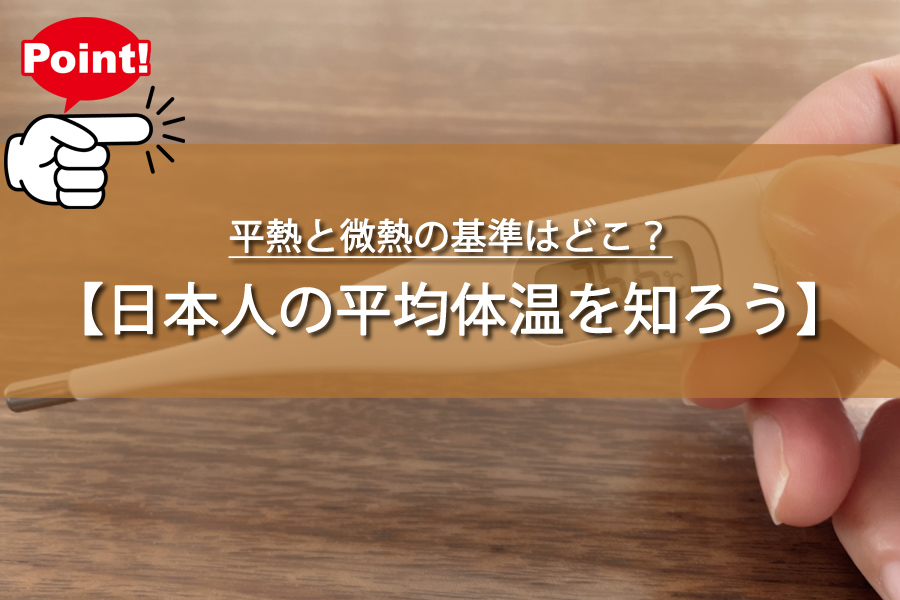微熱と平熱ってどこで基準が分かれるんだろ?
37度を超えても平熱って人もいるみたいだけど…。

「私は平熱が低いの」なんて言い方をすることもあるわよね。
今回は、平熱と微熱の基準や正しい体温の計り方など紹介するわ!
体温が微熱と見なされるのはいくつかの条件下で判断されます。
体温の測定は、医療の基本的な手段の一つであり、体の健康状態を知る上で信頼性の高い方法とされています。
基本的に、微熱とは、37.5度未満の体温を指すと解釈されます。
平熱と微熱の基準はどこ?

微熱や平熱に関しては厳密な定義が設けられていないことも事実です。
発熱の基準は37.5度以上とされており、38度以上を高熱と考えることが一般的です。
平熱は個々人で差があり、健康な成人の場合、一般的には36~37度、またはそれを少し超える程度が普通です。
平熱に関しては、以下のように多様な基準があります。
- 厚生労働省によると、平熱は36~37度とされています。
- 小児における平熱は、36.3~37.3度の範囲であるとされています。
これを踏まえると、微熱の範囲は、37度やそれを少し超えた程度から37.4度までと位置づけることができるでしょう。
日本人の平均体温
日本人の平均体温は36.89度とされており、「平熱」は一般的に36.0度以上37.0度未満、「微熱」は37.0度以上38.0度未満と理解されています。
感染症法に基づく届出基準では、37.5度以上を発熱とし、38.0度以上を高熱と定義しています。
平熱は個人差が大きく、体温が35度台から37度台前半までの範囲にわたる人もいます。
また、がんや肥満、あるいは人種によっても体温は変わり、年齢や時間帯、季節などによっても変動します。
体温が日によって異なることはよくある現象で、これは測定の時間帯、場所、方法による違いによるものです。
正しい体温の計り方

体温の測り方には、正確さを確保するために留意すべき点があります。
通常、体温はどこの部分で計測していますか?
体温は測定部位によって差があります。
口内や直腸での測定が比較的安定していますが、これらの方法は特別な体温計が必要であり、日常的にはあまり実用的ではありません。
そのため、普通の体温計を使用する際には、「脇下」での測定が推奨されます。
体温測定のNG行動
脇下で体温を測る際に、正確な読み取りを妨げる可能性のある行為は以下の4点です。
体温計の固定不足
体温計を脇の深部に置いた後、脇をきちんと閉じて体温計が動かないように固定する必要があります。
動かないようにすることで、摩擦による熱の影響を避け、測定位置が変わってしまうことによる誤差を防ぎます。
脇下が湿っている場合
汗をかいている脇下では、体温計が正確な測定を行えないことがあります。
測定前に脇を拭いて清潔にすることが重要です。
指定された測定時間の不遵守
市販の体温計には、短時間で測定できるものや、数分かかるものなど様々です。
指定された測定時間を守って待つことが大切です。
測定タイミングと環境の不適切さ
食事後は体温が自然と上昇するため、食後直後の測定は避けた方が良いでしょう。
また、極端に暑い、または寒い場所での測定も避けるべきです。
体温は日中と夜で変動するため、自分の通常の体温範囲を理解しておくと良いでしょう。
なぜ体温が上がるのか

発熱は、体がウイルスや細菌と戦っている証拠です。
コロナウイルス感染症はもちろん、風邪やインフルエンザも同様に、体内に侵入した病原体に対抗して発熱します。
発熱のメカニズム
ウイルスが体内に侵入すると、免疫システムが活動を開始し、侵入者を排除しようとします。
このプロセスで、体温をコントロールする脳の部位である視床下部に信号が送られ、体温を上昇させる指令が出されます。
この体温上昇には、筋肉の震えによる熱産生や血管の収縮による熱放散の抑制など、体を温かく保つための複数の反応が含まれます。
ウイルスに対するこの熱産生反応は、免疫細胞がより効果的に働く高温状態を作り出すこと、および病原体が生存しにくい条件を作ることに役立ちます。
熱が出ることの利点と欠点
微熱や発熱は、体が病原体と戦うための自然な反応であり、多くの場合、免疫システムの効果的な働きをサポートします。
しかし、発熱が長期間続くと体力の消耗や脱水症状、心臓への過度な負担など、体に負担をかけることになります。
不快感が強い場合は、体温を下げる措置を取ることが適切です。
平熱と微熱は明確な基準がない まとめ
理解しておくべき重要なポイントは、自分自身の通常の体温、つまり平熱を把握しておくことです。
人によって平熱には幅があり、37.5度以下であっても体内で炎症や発熱の原因が生じていることがあります。
自分の平熱から1度以上体温が上昇した場合、特に喉の痛みや全身のだるさなどの他の症状が見られないかどうかをチェックし、自身の健康状態に敏感でいることが大切です。
最後までお読みいただきありがとうございました!