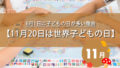冬至には別名というか別の言い方があるみたいだね。
そもそも冬至ってどういう意味があるんだろう?

冬至の意味とか確かにはっきりは知らないかも。
今回は、冬至の別の言い方や意味、語源など紹介するわね!
冬至と言うとピンとくることもありますが、実は別の言い方もあり、そちらは案外知られていないかもしれません。
今回は、冬至の別の言い方や冬至の意味や語源などご紹介します!
冬至の別の言い方とは?

冬至と言えば、一年で最も昼の時間が短く夜の時間が長いことで知られていますが、毎年12月の22日頃には南瓜や柚子などが売られて、冬至が来たことを感じる瞬間です。
冬至とは「日短きこと至る(きわまる)」とされていますが、別の言い方として「一陽来復」と言う言葉で言われることもあります。
ただ、別の言い方で「一陽来復(いちようらいふく)」と呼ばれることは意外と知られていません。
「一陽来復」とは、中国の「易経」に出てくる言葉で、意味は以下のようなものがあります。
- 陰暦十一月、または、冬至の日のこと。
- 冬が去って春がくること。新年が来ること。
- 悪いことが続いた後に、ようやく運が向いてくること。
また、「一陽来復」と言う言葉が生まれた背景には、中国の昔の暦では、10月は陰の気で覆われ、11月になると陽の気が復活し、冬至を境に、陽気が長くなっていくことが関係しています。
つまり、一陽来復とは、衰えていた太陽の力が、冬至を境にして、再び勢いを増してくる日とも言えます。
一陽来復には「新年が来ること」という意味がありますが、他にも、悪いことが続いた後に幸運に向かうという意味も込められているため、今まで良くないことが続いていた人も冬至をきっかけにして、良いことが起こるようになる。との意味もあるんですね。
ちなみに、冬至を英語で書くと「the winter soltice」となります。
冬至の日にゆず湯に入るのはなぜ?
冬至の日と言えば、ゆず湯に入ることを楽しみにされている方も多いと思いますが、そもそもなぜゆず湯に入るかと言えば、ゆず湯は「融通(が利く)」と「湯治」の語呂合わせから、厄払いをして良い運を呼び込むとの意味があるそうです。
冬至の日にゆず湯に入ると風邪をひかないとも言われており、またゆずは長い年月をかけて実る果物でもあることから「長年の努力や苦労が実りますように」との意味も込められています。
ゆず湯は香りがいいだけでなく、縁起物としても重宝されているんですね。
冬至に南瓜を食べる理由は?
冬至の日にはかぼちゃを食べる風習もありますが、これはかぼちゃは「南瓜」と書くため、運を陰である北から陽である南へ運んでくれるようにとの願いが込められています。
また、南瓜にはビタミンやカロテンが豊富に含まれているため、今後も健康に暮らしていけるようにとの思いも込められているんですね。
我が家では毎年、ゆずと南瓜入りのお汁粉を作りますが、どちらも和の食材なので、和菓子にするとより食べやすくなると思います。
冬至の語源や意味

冬至の語源には、諸説ありますが、ゆず湯から連想される「湯治(とうじ)」が由来との説が有力です。
冬至は一年で一番日照時間が短い日で、別の言い方には「一陽来複」があり、この日を境に、再び太陽の力が甦る日と上記でもご紹介しました。
なので、その日を迎えるにあたってゆず湯で身体を清める=湯治(とうじ)が語源となった説があるんですね。
ぜひ、冬至の日にはゆず湯に入って体を清め、厄を祓って、また来年も健康で暮らせるようにと祈りながら、お風呂を楽しんでみてください。
冬至の別の言い方は「一陽来復」だった まとめ
それでは、冬至の別の言い方には何があるのかや、冬至の日にゆず湯に入る理由、南瓜を食べる理由、冬至の語源はどこからなのかなどご紹介してみました。
冬至の別の言い方は「一陽来復」ですが、悪いことが続いていたとしても冬至を境にして、新しい良いことがやってくるという意味があります。
冬至の語源は諸説ありますが「湯治(とうじ)」にあるとも言われているので、ぜひ冬至の日にはゆず湯に使って、厄を祓いつつ、身を清めて、新しい年を迎えてみてください。
最後までお読みいただきありがとうございました!