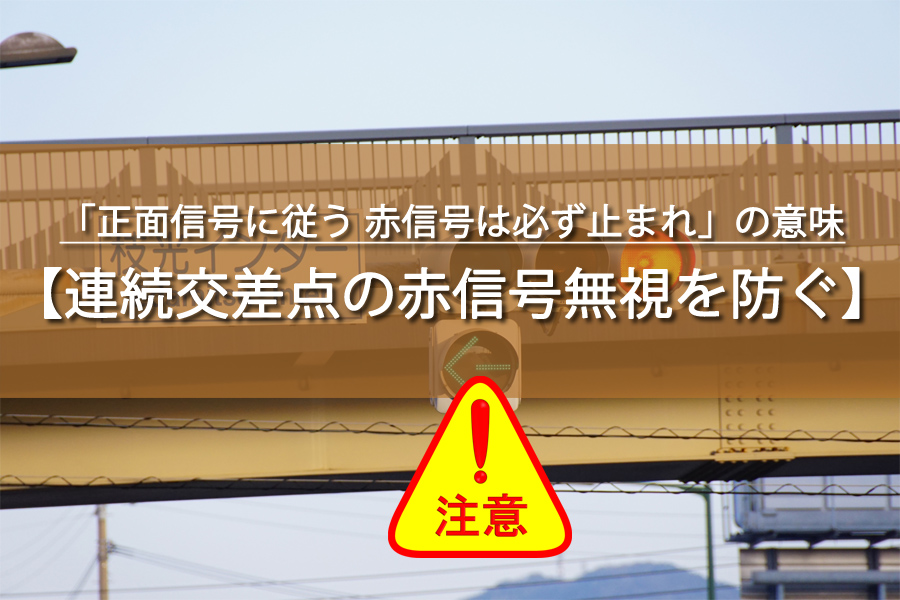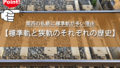「正面信号に従う 赤信号は必ず止まれ」ってたまに見かけるけど…。
当たり前すぎて看板の意味がないんじゃ…。

それが交差点が連続している場合は、必要なこともあるらしいわ。
今回は、「正面信号に従う 赤信号は必ず止まれ」の看板が設置されている理由など紹介するわね!
青信号は進めで、赤信号は止まれというルールは当たり前くらいに浸透していますが、なぜ「正面信号に従う 赤信号は必ず止まれ」の看板が必要なんでしょう?
今回は、「正面信号に従う 赤信号は必ず止まれ」の看板の設置理由などご紹介します!
「正面信号に従う 赤信号は必ず止まれ」は必要?

交差点によっては「正面信号に従う 赤信号は必ず止まれ」と書かれた看板が設置されてますが、そもそも赤信号が止まれを意味することは、今では子供でも知っていることです。
なぜ、わざわざ赤信号に対して止まれと注意を呼びかけているんでしょう?
これには、実は設置すべき交差点があるからとも言われています。
では、「正面信号に従う 赤信号は必ず止まれ」と書かれた看板が設置されている理由を見ていきましょう。
「正面信号に従う 赤信号は必ず止まれ」がある理由
「正面信号に従う 赤信号は必ず止まれ」の看板は、どの交差点にもあるわけではありません。
では、どんな交差点にあるかと言えば、信号機のある交差点が連続している場合に設置されることが多いようです。
問題の交差点をよく見てみると、2つの信号交差点間は50mしか離れておらず、近接しているせいで、右折車が1つの交差点だと勘違いして、信号無視をしてしまう可能性があるため、「正面信号に従う」とわざわざ看板が設置されています。
信号機の設置基準も関係
信号機の設置基準では「隣接する信号機との距離が原則として150m以上離れていること」とされていますが、こちらはあくまで原則であり、道路が狭い日本では距離が離れていない信号機も多くあります。
そのため、信号機の設置基準には、例外として「交通の円滑に支障を及ぼさないと認められる場合は、この限りではない」とされており、今回の「正面信号に従う 赤信号は必ず止まれ」も、例外として踏まえたうえで、事故を少なくするための措置となっています。
逆に青信号にするケースも
上記で、連続交差点の信号機では「正面信号に従う 赤信号は必ず止まれ」の看板が設置されることが多いと書きましたが、東京都などでは逆のパターンも見られるようです。
具体的には、右折車が隣の交差点でも通過できるように、あえて青信号にする例もあるそうです。
黄信号に関する勘違い

青信号は進め、赤信号は止まれなのは周知の事実ですが、意外と多いのが黄信号に対する勘違いです。
黄信号の基本的な意味は、赤信号と同じ「止まれ」であり、黄色信号は「安全に停止できない場合を除き、必ず停止線の前では止まらなければいけない」が正しい答えとされます。
つまり、急ブレーキをかけないと停止が間に合わない場合を除いて、基本的には黄信号は止まらないといけません。
よくある勘違いなので、今回ご紹介してみました。
「正面信号に従う 赤信号は必ず止まれ」は交差点による まとめ
それでは、「正面信号に従う 赤信号は必ず止まれ」の看板が設置されている理由や黄信号に対する勘違いなどご紹介してみました。
「正面信号に従う 赤信号は必ず止まれ」が設置されている理由は、信号の間隔が狭い連続交差点での車の事故を防ぐためだったんですね。
赤信号が止まれは当たり前ですが、その当たり前を本当の意味で当たり前にするためにも、看板の設置理由を知って、安全運転を心がけてみてください。
最後までお読みいただきありがとうございました!