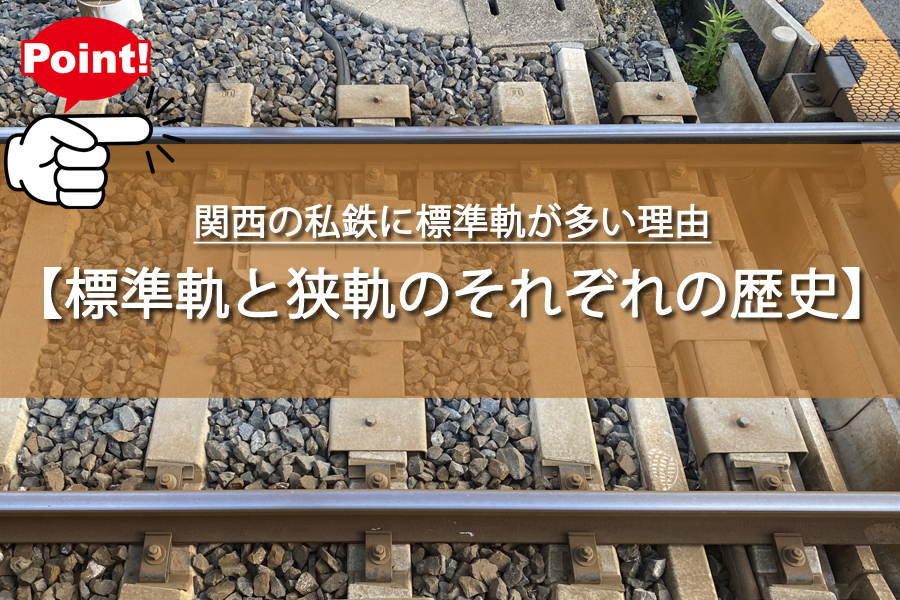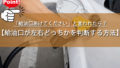関西の私鉄には、なぜか標準軌が採用されてるケースが多いよね?
なぜ、私鉄には標準軌と狭軌があるんだろ?

説にもいろいろあるけど、大きな理由は路面電車として開発されたかららしいわ。
今回は、関西の私鉄に標準軌が採用されている理由など紹介するわね!
関西の私鉄には、なぜか標準軌が多く採用されていますが、なぜ他の私鉄には狭軌が多いのだろう?と疑問に思ったことはありませんか?
今回は、関西の私鉄に標準軌が多く採用されている理由などご紹介します!
関西の私鉄に標準軌が多く採用されている理由

関西の私鉄に標準軌が多く採用されている理由は、京急、京王、京成、西鉄などがそうであるように、軌道=路面電車として開業したからです。
近年までは、鉄道と軌道は法律上で分かれていて、鉄道は軌間が1067mmと設定されていました。
1067mmではない私鉄を見た場合、名鉄と南海を除き、JRと並走していることがわかりますが「なぜ、名鉄は東海道本線、南海は阪和線とも並走するのに1067mmなのか?」という疑問がわくかもしれません。
以下に、名鉄と南海が狭軌としたのか、理由などご紹介します。
名鉄が狭軌を選んだ理由
名鉄では、名古屋と岐阜・津島方面を結ぶ路線で、名古屋電気鉄道と呼ばれる会社が、他の会社と合併して成立している過去があります。
この会社は名古屋市内の路面電車も持っているのですが、開業は1898年と古かったため、当時は京急や阪急などの標準軌の私鉄はまだ開業していなかったようです。
こちらの路面電車が「鉄道」として名古屋市内を走ることを認められ、結果、郊外の路線も1067mmで建設したと言われています。
南海が狭軌を選んだ理由
南海では、私鉄が1885年に阪堺鉄道として開業した過去があります。
実はこの時はまだ「阪和線」がなく、阪和電気鉄道と呼ばれる別の私鉄が、後の1929年に開業させました。
その後、南海の買収を経て、1944年に国有化され阪和線となりましたが、競合する国鉄がなかった影響で、1067mmで建設できたとも言われています。
標準軌と狭軌の違いは?
日本には二種類のゲージがありますが、ゲージとは二本のレール幅を指し、新幹線や関西の私鉄がメインで使う「標準軌」と、JR在来線やその他の私鉄が使う「狭軌」などの違いがあります。
当然、ゲージの幅が違えば、新幹線と在来線は同じ線路の上を走ることはできないません。
貧乏だった明治維新後の日本であれば、安い方が好ましかったのですが、車両が小さければ、輸送力=お客さんや載せられる荷物の量が少なくなるのは間違いありません。
また、狭軌では車両の安定性が悪くなるため、底面が大きい方が倒れにくい=標準軌の方がスピード出る計算です。
関西の私鉄では、狭軌を利用するケースも多いのですが、コストが安いとの理由が大きいと思われます。
関西ではインターアーバンが主流だった

関西の標準軌の私鉄は、そのほとんど(阪神・阪急・京阪など)が、軌道出自のインターアーバン(都市間連絡)と言われています。
初期の都市型の軌道は、鉄道馬車の名残もあったことで、標準軌またはそれに準ずる軌間(トーキョーゲージと呼ばれる4フィート6インチ)で作られていたんですね。
関西でも、最初から鉄道として作られた南海や神鉄は狭軌で建設されています。
ちなみに、上記でも少し触れましたが、南海は2フィート9インチで開業した後、狭軌に改軌しています。
南海は当初は蒸気の阪堺鉄道だったため、阪和間を独占し、貨車直通もあったので、そもそも標準軌はあり得えない選択肢だったんですね。
その後、阪和電鉄が先行して誕生した結果、国有化が行われていれば、南海が電化して、標準軌に改軌という選択肢も可能性として残されていました。
ただ、実際には阪和の方が後で、阪和は南海に吸収されてから国有化されたので、その流れにはならなかったそうです。
関西の私鉄に標準軌と狭軌が採用された理由 まとめ
それでは、関西の私鉄に標準軌が採用されている理由や今でも狭軌が使われている理由などご紹介してみました。
標準軌と狭軌の違いは「幅」ですが、どちらを利用するかで、輸送量やスピードが違います。
現在関西の私鉄に標準軌が多い理由は、JRと並走するためというのも理由としてありますが、ざっくり言えば、競合の関係で、現在では標準軌が多く採用されています。
最後までお読みいただきありがとうございました!